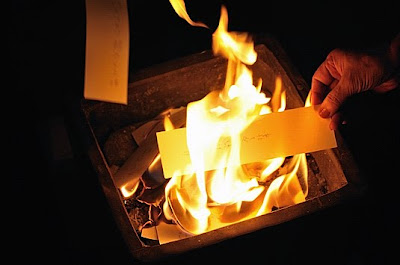「俳句~近くて遠い詩型」という
現代歌人集会のシンポジウムに行ってきました
西原天気0外国人による日本人論は売れる、という時代が長く続きました。古典的なところでルース・ベネディクト『菊と刀』、李御寧『「縮み」志向の日本人』、『日本人とユダヤ人』は実際はどうあれイザヤ・ベンダサンの名義でした。自分たち(日本人)は外(外国人)からどのように見られているのか。なんだか貧乏臭い自我意識ですが、俳句愛好者たる私もまた、短歌イベントに「俳句」の2文字があったからこそ、遠く神戸まで出かけたのです。
というわけで、現代歌人集会春季大会「俳句~近くて遠い詩型」(2014年7月19日)に行ってきました。
ムダにまどろっこしい前置き、ご容赦。つまり、俳句というもの、歌人さんたちの目にはどのように映っているのだろう?という興味関心です。神戸は、まあ、知人に会うという用事を絡ませるので、わざわざこれだけに、というわけではないのですが、朝9時50分のぞみ105号で会場には13:00ギリギリか、少し遅れて到着でした(3時間余りの小旅行)。
なお、7月に春季? というところは、こだわるところではないようです。次回は秋季ですが、ずいぶん寒くなってからのようですし。鷹揚。いいですね。
●さて、イベントは次の3つから成ります。
1)基調講演 大辻隆弘(現代歌人集会理事長) 正岡子規における俳句と短歌
2)講演 高橋睦郎
3)パネルディスカッション 塩見恵介、大森静佳、荻原裕幸、魚村晋太郎(進行)
ひとつずつ、レポート、というより簡単な感想を。
1大辻隆弘講演は、正岡子規の短歌改革と俳句改革をコンパクトに解説。ひじょうにわかりやすかった。
短歌改革の要点は(レジメより)、
1 透明な文体の確立
2 過剰な助辞(助詞・助動詞)の排除→名詞の重視
3 名詞の映像喚起力
4 「視点」の位置・作者の立ち位置
補足すると「1」は、「ですます」「だ」など対人関係を示す文体を避ける。結果、「なり」の語尾を推奨。
俳句改革は、短歌改革の骨子をほぼそのままあてはめたもので、そのうえで、短歌の俳句との違いは、「時間を含みたる趣向」「主観を自在に詠みこなし得る事」。
以上、現在の俳句、そして(私の想像するところの)短歌においても、ほとんど古びることなく通用する「総論」でありまして、ほんとうにもう、「
子規、あんたすげぇよ!」なわけです。
以上のようなことは、勉強をされている俳人諸氏にはすでに常識かもしれませんが、誰もが「勉強」しているわけではないので(私も恥ずかしながら、そう)、とてもタメになりました。
というか、大辻講演は、語り口、まとめ方(レジメを含め)、引用の量など、いずれをとってもよろしきあんばいでした。
2高橋睦郎講演は、「うた」という広い視野・脈絡から短歌と俳句をとらえたもの。
ごくごく短くかいつまむと(私の記憶の範囲で短く言うと)…
日本文学史の中心には「うた」があり、「うた」とは神への恋である。そこには、自然への恋、人への恋の2つがある。一方、かつての歌集の部立てとして「雑歌」「相聞」「挽歌」を挙げ、雑歌の系統に「季の歌」があり、それが連歌となり発句が俳諧となり、さらに俳句となる。
こうした歴史的に長大なスパンの話を、巧妙にエピソードなども交えつつ、なので、聴衆を飽きさせません。
忌日季題に端的な「死者文芸」としての俳句、一方、本歌取りの伝統を失った短歌といったあたり、あるいは多岐にわたる話題は、この講演だけではコトバ足らずの感もあるが、そこは高橋氏の著書ほかに当たれ、ということでしょう。
さて、大きな歴史の中に、いまの俳句を捉えるということは、例えば、次のようなことです。
「
俳句は、自分ひとりが書くのではない。多くの死者の手(伝統)がいっしょになって、自分に書かせている」。高橋氏が語る、そうした作句上の経験的実感のようなものは、少なからぬ俳人が首肯するところだと思いますが、高橋氏の俳句をある程度たくさん読んだ者の耳には(私は『百枕』等を愛読)、さらなる納得感をもって響きます。
このあたりは、かなり深くてややこしい展開も可能だろうけれど、講演は足取り軽く、次の話題へと向かったので、ここでもあっさりと終わっておきます。
ところで、この講演のバラエティ豊かな話題のなかで、私がある種「啓示」のように受け取ったのは「
新体詩」の一語でした。
講演の主流に位置づけられた語ではない。また新しい知見でもない。明治史に出てくる、
あの「新体詩」。
考えてみれば(と、私は講演の流れからすこし離れて考えてみたわけです)、西欧の「詩」が当時翻訳されて、日本の「うた」の歴史に流れ込んだ。以降、この「詩」のノリ(この手の抒情)がかなりの存在感をもって、私たちに覆いかぶさり続けた。
ここでちょっと飛躍しますが、あとで触れるパネルディスカッションにおいて、歌人が挙げた俳句作品のラインナップは、「詩的な俳句」
〔*1〕が多いというのが私の感想でした。ポエティック、ポエミー、どちらでもいいのですが、つまり、「新体詩以降の流れ」の色濃い俳句
〔*2〕を、歌人は好む傾向があるのかもしれない。おぼろげながら、そんな印象をもちました。
短歌はまったく不案内ですが、塚本邦雄以降、さらには昨今の「口語化」(このへん間違っていたら叱ってくださいネ)を見ると、「新体詩以降の流れ」が作り上げたノリ・心性の色濃さを、強く思ってしまいます。
何を言うのだ? 西欧化
〔*3〕は、いまの私たちが洋服を着ているようなもので、いまさらのように扱うことはバカげている、といった声もありましょう。
けれども、「生まれたときから、そうだったもん」とは言わず、つまり、所与のものとして片付けることをせず、ちょっと洗い直す作業があってもいいのではないか、と思ったのですよ。「新体詩」という3文字から。
もっとも、高橋講演にとっては、「そんなところに引っかかられてもなあ」といったことなのですが、まあ、そんなことも考えたわけです。
ついでに言えば、新体詩以降の「抒情」に、短歌は、俳句ほど疑いを持っていない
〔*4〕、というのが、私のイメージです。あくまでイメージ。
3モノにアプローチするとき、2つの方法があって、1つは、切り口なり推論から出発して具体(短歌・俳句作品)へと触れる(演繹といっていいかもしれません)、1つは作品から出発する(帰納)。
塩見恵介氏(俳人)と歌人3氏、大森静佳、荻原裕幸、魚村晋太郎によるパネルディスカッションは、後者を選び、各自が「作品」挙げ、それについて語ることにこだわったものでした。そこから何らかの一般則や「最近の潮流」が見えれば、という目論見もあったかもしれませんが、そこまでは行かなかった感。しかしながら、茫洋とした一般論(総論)で、空中戦が展開されるよりも、作品を目の前にしての話のほうが、聴衆に親切、というところがありますから、これはこれでいいと思いました。
パネラーが俳句と短歌を1つずつ作って(兼題「神」「戸」)持ち寄るという趣向もありました。そこでひとつ。魚村晋太郎氏の俳句《虹きえて戸棚の奥の正露丸》についての討議。《虹きえて》という部分に話題が及んだときです。
あっ、ここで、子規でしょう。大辻講演にあった〔
4 「視点」の位置・作者の立ち位置〕へと話題を展開すればいいのに。「作者はいったいどこにいるんでしょう?」という…
〔*5〕。
こう、心の中で手を上げて発言したのは、私だけでないでしょう。
(これは「虹きえて」の取り合わせが良いとか悪いとかといった問題ではなく。また「作者」は(悦ばしく)どこにもいないという把握も含めて)
パネルは、その方向には向かいませんでしたが、聴いている私たちは、3つの演し物を串刺しにして、あるいは立体的にこの日のシンポジウムを味わえました。こういうこともまた、3つの別の講演を通して聴く愉しみですね。
あ、そうそう。塩見氏が「気になる俳句(次世代型)」として挙げた《
「この雪は俺が降らせた」「田中すげぇ」 吉田愛》がパネルでの注目度が高かったことも報告しておくべきでしょう
〔*6〕。
現実世界から採取(引用)してそのまま句になるパターンは古くからありますが、この場合、発語に「雪」という季語が含まれている点が面白く、いわゆる手柄でしょう。カギ括弧はどうにか処理してほしいところです。そこまでていねいに「採取したんですよ」と言わなくてもいい気はします。
短歌なら、このあと作者が七七を加えるが、俳句はそのままでもオーケーなんですね、という指摘もあったように記憶しています(この七七で作家性や能力が問われるのかもしれません)。
その意味では、俳句は、ずいぶん
ズボラで、いいかげんです
〔*7〕。ひょいとつまんでそのままでいいのですから。
メインディッシュじゃなくていい。素材を活かした「向付」でも一句になる。それが俳句といったところでしょうか。
●このシンポジウム、ちょっと遠いので迷ったのですが、出かけてよかったです。いろいろな方の話が聴けたのもよかったし、その後、いろいろな方にご挨拶が叶ったのもよかった。
ここには書きませんでしたが、その夜、またその次の日、俳人さん、柳人さんと一緒の時間を過ごせたのもよかった。フォーマルな話、そうじゃない話、どちらにも妙味があります。
〔了〕
〔参考〕
■歌人の正岡豊さん @haikuzara が「歌人集会」を振り返る
≫
http://togetter.com/li/696933■荻原裕幸さん(@ogiharahiroyuki)=パネラーと曾呂利さん(@sorori6)が「歌人集会」を振り返る
≫
http://togetter.com/li/697936〔*1〕ポエティックな俳句作品とは、例えば《あぢさゐはすべて残像ではないか 山口優夢》。レジメの2箇所に挙がっていた。
この句、俳句方面でも注目度や評価が高いようだ。私の印象は「上等なポエム(ポエミー)」。上等は上等だろうけれど、ポエムはポエム。この作者・山口優夢の他の句に、私の好きな句が多い。
〔*2〕この件は、素材の話ではなく、心性、抒情、感興の「質」であることは、念を押しておきたい。「新体詩」以来の抒情と対極にあるのが、(例えば「電気もガスもない暮らしか!」と思えるような)伝統的素材に満ちた作風、ということではまったくない。
〔*3〕西欧化に関して、「子規の俳句」がこの時期の西欧化(西欧事物の怒濤的流入)と密接に関連したことは、秋尾敏『子規の近代―滑稽・メディア・日本語』(1999年・新曜社)に、また
橋本直「俳句の自然 子規への遡行」にあるとおり。
〔*4〕俳句の内部でも、抒情をめぐっては亀裂がある。いわば「詩」的な俳句と「俳」的な俳句が対照的に存在する。ただし、俳人が二分されるわけではない。1冊の句集のなかに「詩」と「俳」の2成分が混在するケースのほうが、むしろ多いだろう。
〔*5〕掲句は、行為者が出てこない句なので、視点や立ち位置の複数化・遍在はあまり気にならないが、このところ、行為者がどこにいるのかわからない取り合わせもよく目にする気がする。季語が「かなり自由に」扱われる、あるいはムードで使用される傾向がめだつ。繰り返すが、良い悪いの話ではない。
同時に、リアル・アンリアルとも無関係。抽斗に国旗がたなびいてもいいし、火星に桜が散ってもいい。視点の問題。「視点」とは作者のものであると同時に、読者への「見させ方」でもある。写生にもファンタジーにも、見させ方、夢見させ方がある。
〔*6〕この句について、私個人の感想は、「おもしろい」。けれども、好きかと問われれば、「ノー」。パッと見ておもしろがれる句が、その夜、また思い出して好きと思う句、愛せる句とは限らない、といったところです。
余談ですが、酒席で、《「この雪は俺が降らせた」「角川春樹すげぇ」》といったパロディが出てきそう。パロディが生まれやすいのは、残っていく句の条件のひとつ。
〔*7〕これはもちろんのこと、俳句の美点。
![]() |
| レジメの充実が、シンポジウムの誠実さを物語る。 |