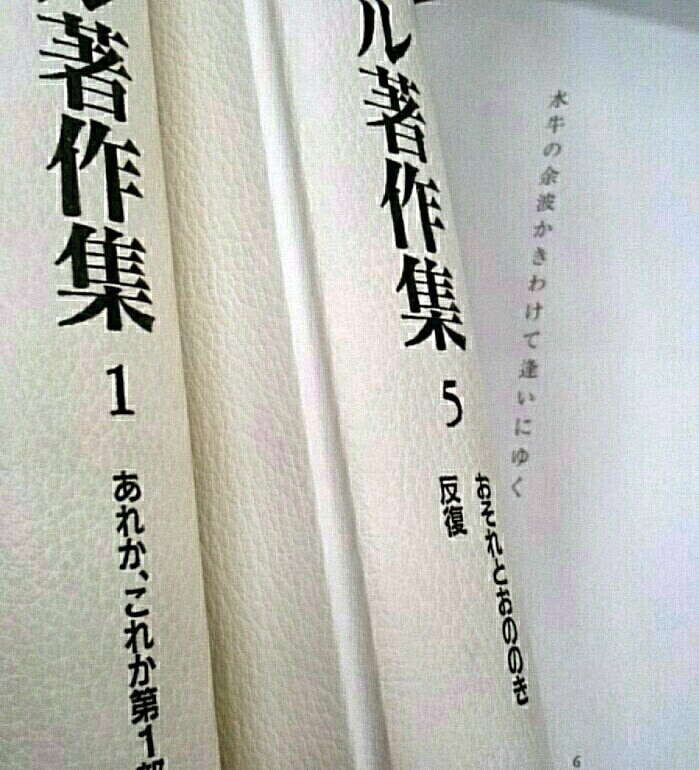【2014角川俳句賞 落選展を読む】3.みんなおなじで、みんないい?依光陽子≫ 2014落選展11人の鑑賞が終わって、折り返し地点。次の角川賞締切まであと5ヶ月である。
前回「絶対に成功しない素材ランキング」と書いたところ、先日の句会で他にどんな素材がNGかという話題で盛り上がった。
以前、角川『俳句』に常套句について書いたことがあるのだが(
平成19年5月号特集《類句・類想をこうして避ける》の<死して常套拾ふものなし>)、5年たってもあまり状況は変わっていないのだなぁと改めて思った。
「ひこうき雲」「観覧車」「誰々の生誕地or終焉の地」「樹齢○百年の松」「ヘリ」など、成功しないという意味は、それらを扱った俳句はごまんと目にするが、佳句を見たことがない、ということだ。
俳句文学館で全国の俳誌を片っ端から読んでみれば明らか。皆等しく詩情を掻き立てられ、皆同じように書き留める。例えば、ひこうき雲もクレーン車も斜め○○度の傾きで空に刺さっている。
観覧車の傍らには太陽や月がある。料理俳句、名画俳句、女優の名前の薔薇俳句。季題ラ・フランスが60歳代女性作者の句集に頻出する不思議現象など、挙げればきりがない。
人の個性はその人だけのものだ。生きてきた環境も取り入れてきた影響も全て違う。だから俳句だって違うものが出来るはずなのに、どうして同じような句を良しとしてしまうのか。
皆と同じで安心する「シゾフレ型」、たとえ自覚はなくとも俳句界はシゾフレ天国、模倣天国である。俳句という詩型特有の制約と無数に生み出された他者の作品の中で新しい句を書くことは本当に難しい。
自分が簡単に気付くものなど、誰もが簡単に気付くのだ。「誰かが詠んだような句は詠まない」と腹をくくるところがスタート地点だと思う。
12.ふらんど(さわだかずや)春の句のみの50句。中盤、うつの句が並ぶ。この作者に限らず、うつを詠んだ句を句集などで度々目にするようになったのは近年顕著だ。「精神病んで」「不快」「嗚呼死にたし」などネガティブな言葉が連なるとさすがに読んでいて息苦しくなってくる。<
半裸にてつくしを摘んでゐる集団>はどこかラース・フォン・トリアー的で許容範囲だが、「痰」「ビーム」など度が過ぎると意図をはかりかねる。うつの句も双極性障害の句も、その病状について詠まれても読者は困るものだ。またそうした素材を詩にまで昇華させることは至難の業だ。
強烈な言葉を直接読み手にぶつけるだけでは句は立たない。それがどんなに厳しい経験であっても、客観的に作品を検証する目と、完成度がなければ、読み手の心を揺さぶることは出来ないだろう。なぜなら、書かれた時点で言葉はイメージになるからだ。
耳の奥熱き遅日を過ごしけり さわだかずや
花ですから死んでしまつてよいさうです一切無常にて蜆汁おかはり気になった句。
一句目。「耳の奥が熱い」とは決して良い状態を表してはいない。「耳の奥が熱い」ことで、太陽が出ている時間が一層永く感じられる苦痛。だがこの句は他の憂鬱な作風の句に凭れ掛かっていない。遅日を従来とは別の角度から表現することに成功している。
二句目は万朶の花明りが死を誘う。否、誘われたのではなく「死んでしまってもいい」という言葉がふと降りてきたのだろう。作者は理由を見つける。「花ですから」、つまり桜がこんなに咲いているのだから、と。桜と死。文学上、民話上語りつくされた二物からこの句は起草され、歩き出す。そして漠然と死を許されたこの人物は決して死なない。それが俳句作者としてのしぶとさであり、この句のしぶとさでもある。
三句目、一切が無常だという諦念に思考を留めながら、効能たっぷりな蜆汁をおかわりしてしまう生き物としてのせつない事実。この矛盾は取り除けないものとして心に刺さる。
<
韮やはらかし人妻はさりげなし>は桂信子の<
ひとづまにゑんどうやはらかく煮えぬ>、<
やい鬱め春あけぼのを知りをるか>は江國滋の<
おい癌め酌み交はさうぜ秋の酒>の先行句がそれぞれ口をついて出て来る。ましてうつを扱ってこの薄さでは心の網にかからない。たとえ先行句を踏まえたのだとしても、その句を超えない限り類想句の域は出ない。
もろもろ書いたが、この50句からは過去の自分に抗う歯ぎしりが聴こえて来た。それがこの作者本来の作家性の恢復と信じたい。
13. 封境(杉原祐之)正統派かつスケッチ風。省略の利かせ方、句の佇まいは否定しない。ただ、中盤のほんの数句の海外詠(?)には異質な印象を受けた。<
ターバンと付髭映す泉かな>から<
引越の果て風鈴の鳴りにけり><
播州の室津の浜の蝦蛄を漁る>でやや唐突に国内詠に戻りさらに風土詠へと移行する辺り。50句のどこに読みのピークを持って来たかったのだろう。なんでも俳句に出来てしまう人は、何を書かないでおくか、顎を引いて考えてみるべきであろう。
子を風呂に入れたる後の夕涼み 杉原祐之
ポストへと落葉の嵩を踏みながらプレハブの目印をつけ冬の芝中で、この三句に立ち止まった。
一句目、まだ幼い吾子だろう。子どもを風呂に入れることは若い父親には大仕事だ。夕涼みをしている姿から安堵感が伝わってきて清々しい。
二句目は平凡なカットだが作者の息づかいが感じられた句。落葉を踏む音と心音が重なっているよう。ポストは落葉の嵩を踏まなければ辿りつけない場所にある。「嵩」という言葉が辺りの風景や、ポストの中にあるはずの手紙や葉書の重なりを連想させる。郵便物を投函する瞬間のちょっとした覚悟に至るまでの、短いけれどまっすぐな時間。
三句目、仮設住宅か工事現場のプレハブか。芝の上にそれを建てるための印をつけた。少しだけ根本に緑が残る冬の芝の枯色と目印をつける人の背中。きっと同じような色の作業着だ。冬の芝はやがてプレハブの下になり完全に枯れてしまうだろう。とまれ、冬の芝の広がりがよく見えてくる。
全体的に季題の斡旋は悪くない。あとはかな遣いのうっかりミスをなくし、50句に統一性が欲しいところ。もう一歩踏み込んでモノを見ることで、さらに見えてくるものがあるはずだ。
14. 新機軸(すずきみのる)<
壺焼のさみどり残す肝の尖><
その中に制服もゐて御命講><
電線とひとつの影に夕燕>など俳句を作り慣れている作者だと思った。
摘みきたるオクラ十指をはみ出して すずきみのる
まさに素手で摑んだ句。両手に余るほどのオクラを摘んできた。大きく広げた指の間からオクラの先端が見える。指の間からはみ出したオクラが手の棘のようで、オクラの表面のチクチクとした感触と相俟っている。
なめるごと寄りくる波に千鳥翔つ 煮られつつあり白繭もその夢もタイトルは「新機軸」。50句最後の<
初句会この人にこの新機軸>から採られている。新機軸とは初句会にふさわしい心意気。またこの作者にとっても上記二句は、数年来の落選展の作品に比べると出色と言えそうだ。
一句目の「なめるごと」は千鳥のいる干潟に寄せて来る波の表現として無理がない直喩だと思う。干潟を舐めるように平らかに静かに寄せて来る波。長い脚が浸り、砂に刺した長い嘴が浸り、そして汐がある高さになったとき千鳥は翔つ。そこに至るまでの千鳥の行動も見えてくる。
二句目。あれほど盛んに音を立てて桑を食べていた蚕の蛹は、繭の中で夢を見ているかのよう。一読メルヘン調だが内容は厳しい。蚕は羽化することを許されない。煮られ殺されて繭を剥ぎ取られる運命だ。羽化してその翅で羽ばたくという夢もまた儚い。
手練の作者だけに、既視感のある句やかな遣いが間違った句が散見されるのは実に勿体ない。句を厳選し、十分に精査し、さらなる「新機軸」を開拓してゆかれることを期待したい。
15. 室の花(津野利行)冒頭五句はさておき、身の丈に合った自分の言葉で句を書いている点に好感を持った。
夏掛は妻を小さく包みけり 津野利行
大学は辞めたと笑ふ生ビール何もなき父の形見や心太一句目。夏掛は寝ている人を嵩なく見せる。「小さく包みけり」に妻との微妙な距離感や、押しつけがましくない愛情を感じる。寝姿も見えてくる。夏掛という季題の効果がある。
二句目。大学職員か、はたまた大学生の友人か。「大学の方はどう?」「実は辞めたんだ」そんな会話があって、友が笑った。いろいろな葛藤を経たであろう複雑な笑顔。この生ビールはとても切ない。
三句目。眼目は「心太」の斡旋だろう。雲色のつるんとした心太。昔ながらの心太の突き器を使ったものであればなおさら、その押し出した後の空虚さは一入である。喉に滑ってゆく心太の冷たさ。「何もなき」に、父の死をすでに遠く認めることが出来るようになった作者の心が、読み手の心を押し出す。
室咲は枯れぬ気でゐたかもしれぬこの作者もタイトルの語を含んだ句がラストに置かれている。室の花を年老いた肉親の生前と深読みし、悲しい句だと思った。そんな深読みを誘う伏線となる句が50句中にいくつか点在していたからだ。だが一句単独で読んだとき、室咲の効果が見当たらないのである。私は改めて、一句として立つことと、50句として立つこととの違いを考えさせられた。
16.バンテージ(谷口鳥子)面白そうな句が出てきた。
以前、50句全句動物園で作った句で構成された応募作品があった。一句一句の完成度も高く感心してしまったのだが、この作品は全句ボクシングをテーマにした句で異色。「誰も詠んでない句を詠んでやる」という意気込みがいい。こういった元気のいい作品が読めるのが落選展の醍醐味だろう。
現代かな遣いである。
ヘッドギア何度も直す熱帯夜 谷口鳥子
容赦なく打ちくる小五の日焼け顔作者も熱いけれど句も熱い。「小五の」は中八かつあまりに粗雑な省略で、子どもだとわかるので不要と思いながらも「容赦なく打ちくる」濁りのない眼差しが気持ちいい。
蝉の鳴くリズム外してストレートのっぺらぼうの月と並んでジム帰りジョグダッシュジョクダッシュ十一月膝と腰と首でリズムを夏来たる無理矢理季題を入れたような句も少なくないが、このあたりはいい具合に季題が収まっている。
一句目。ジムの壁を突き抜けて来る蝉しぐれの中でのストレートの練習。蝉の鳴くリズムをわざと外してみる。ちょっとした遊び心。
二句目。のっぺらぼうの月はあたかも丹下段平。一日の練習を終えた充足感が「並んで」という言葉に込められている。
三句目。もし私がボクシングを始めたら、この句を念じながらジョグ、ダッシュのインターバルトレーニングを繰り返すと思う。あきらかに破調だが繰り返し口遊んでいると、なんとなく年の瀬へ向かっていく冬の空気感が出てくる。「十一月」が或いは動かないかもしれない。
四句目。俳句も運動もリズムが大事。なるほど、ボクシングは膝と腰と首でリズムをとるのか。「夏来たる」は漲るエネルギーを代弁している。
さて、もしこの50句で受賞したらこの作者は受賞第一作にどんな句を書いただろうかとふと思った。次回は不用意な贅肉句は落としつつ、完成度も磨き上げてほしいと思う。
17. 空車 (高梨章)春の日の金の夕べを空車(むなぐるま) 高梨章
タイトルの句である。俳人・山田みづえの父である国語学者・山田孝雄の『「むなぐるま」考』の中から言葉を借りれば、「空車・むなぐるま」は「のらぬ車也、迎などに人のこぬ心也」(匠材集)とある。私は特に「人のこぬ心也」という部分が気に入っている。むなぐるまという言葉は主に院政鎌倉時代の語で、平安朝から鎌倉時代の間にだけ使われたようだが、作者はこの古い言葉を一句に入れた。「の」でたたみかけてゆく手法はこの句に限ってはあまり気にならない。時代を遡らせ、駘蕩とした世界へ読み手を誘う。春の金色の夕べをゆく空車の音なき音。眩しさと虚しさ。印象深い句だ。
秋の灯台 いつぽんの蝋燭をひろふ分かち書きはこの一句だけだが、悪くないと思う。秋の灯台といつぽんの蝋燭を拾った事実の間に空白が必要だったからだ。解釈は不要。そのまま受け取ればいい。読み手の席は用意されている。
他にも<空席をつくるたちまち月あがる>や<月の力すこしゆるみぬ時計店>も二つの事柄にあたかも関連があるように現実と非現実の間、意味と無意味の間に句世界を構築している。日常語と旧かな遣いの起こす幽かな摩擦が醸し出す何か。<手袋は暗くなるころおそろしき>など、進もうとしているのは鴇田智哉的な志向と見るべきか。
アスタリスクの章立てで、春・冬・秋・夏という不規則な並びにしてある。面白い試みだが、最後の夏の部に入っている句があまりよろしくないのが残念。凝っているわりに<秋の朝きのふの雨の光かな>という至極平凡な句が入っていたり、「蟻地獄」「蝸牛」の連作は雑すぎる。もっと根気強い練り上げが必要。それ以外は、ある虚無感が漂っていて「空車」のタイトルが全体によく行き渡っていると思った。
● ≫ 0. 書かずにはいられなかった長すぎる前置き≫1. ノーベル賞の裏側で 依光陽子≫2. 何を書きたいか