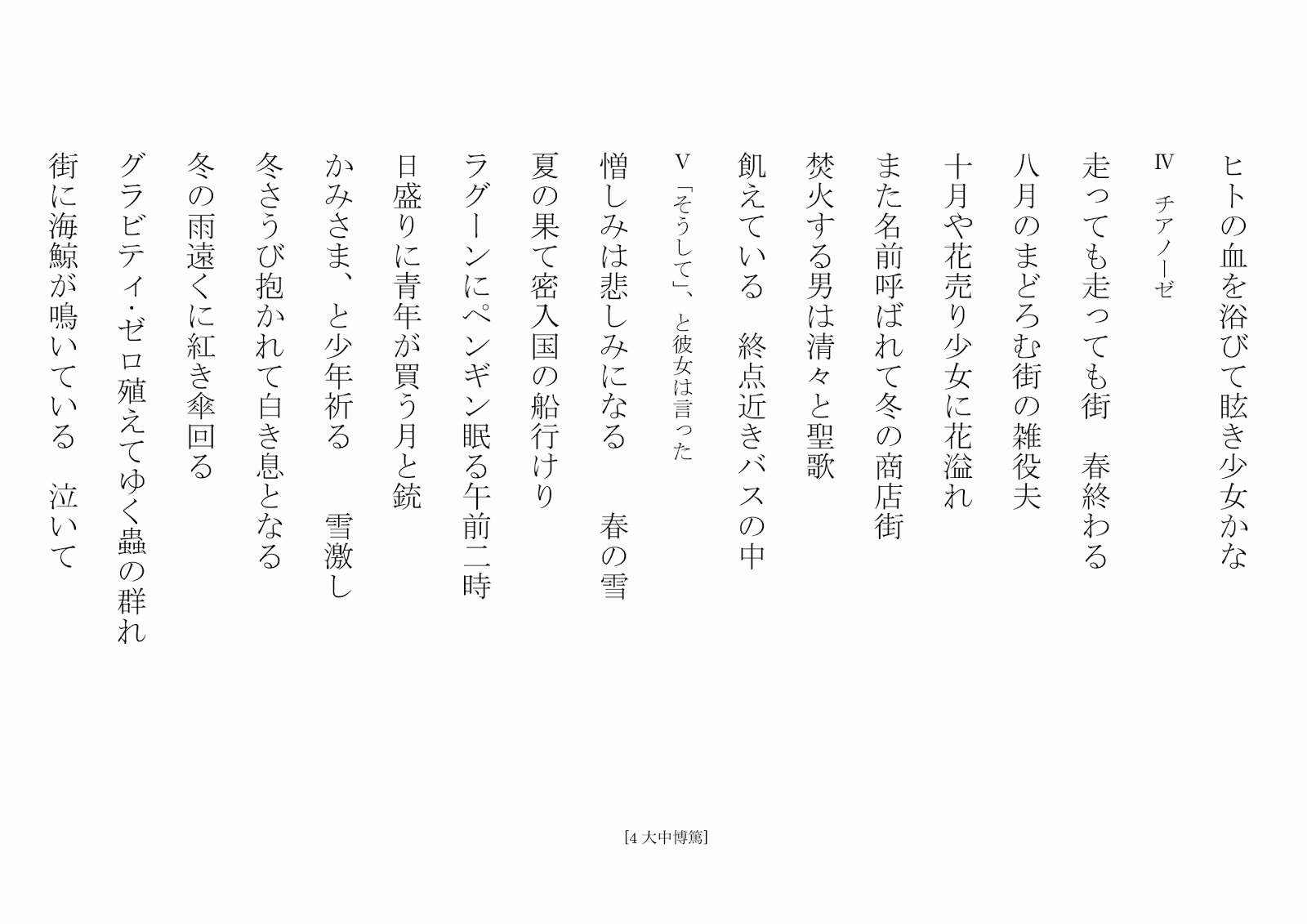↧
落選展2014_4 魂の話 大中博篤
↧
落選展2014_3 線路 上田信治_テキスト
3 線路 上田信治
てふてふや中の汚れて白い壺
春の日に見下ろす長い線路かな
霞みつつ岬はのびてあかるさよ
桜さく山をぼんやり山にゐる
ひよどりのゐる電線も花の中
餃子屋の夕日の窓に花惜しむ
鯉のぼりの影ながながと動きけり
かしはもち天気予報は雷雨とも
ゆふぞらの糸をのぼりて蜘蛛の肢
珈琲の粉がすずしい月あかり
ゆつくりと上れば月見草の土手
晩夏の蝶いろいろ一つづつ来るよ
朝顔のひらいて屋根のないところ
状差に秋の団扇があつて部屋
草を踏む犬のはだしも秋めくと
われもこう山の手前に雲のある
鵯のよく鳴くけふの今日限り
秋の薔薇行けばどこまで同じ町
つめたい手おほきな窓に紅葉山
雨樋を石蕗の花へとたどり見る
靴べらの握りが冬の犬の顔
北風の荒れてゐる日の水たまり
寒晴やテトラポッドの脚組み合ふ
ふくらはぎ伸すや日の照る冬の海
石に吹く風の聞こえるかぜぐすり
江ノ島のコップの水や麗らかに
クロッカス団地一棟いま無音
手に水の触れる速さに春の雪
さへづりの向かうに白い村の道
たふれゆく春の夕べのアロエベラ
仔猫野良あけがたなれば慕ひくる
そらまめや雨ふつてゐる窓ひとつ
栗の木が咲いてモルタル壁の家
犬を見るかしこい犬や夏の庭
蒲の穂の先からなほも伸びるもの
サルビヤの町に帽子の若い人
白布のうへ四つの同じ夏料理
冷蔵庫に西日のさしてゐたりけり
秋の山から蠅が来て部屋に入る
バスに見る川をうづめて葛の花
月今宵みづの出てゐる水飲み場
煙草買ふと云うて別れし良夜かな
あの山におほきな岩や紅葉づれる
鳥威なほして今日を終はる人
冷ゆる田と家具工場のありにけり
スケーターズワルツ丘から見る町は
地には霜やさしい人たちの自転車
網フェンスに絡みて枯れてそよ風よ
やすみなく暮れゆく空や毛の帽子
その年は二月に二回雪が降り
てふてふや中の汚れて白い壺
春の日に見下ろす長い線路かな
霞みつつ岬はのびてあかるさよ
桜さく山をぼんやり山にゐる
ひよどりのゐる電線も花の中
餃子屋の夕日の窓に花惜しむ
鯉のぼりの影ながながと動きけり
かしはもち天気予報は雷雨とも
ゆふぞらの糸をのぼりて蜘蛛の肢
珈琲の粉がすずしい月あかり
ゆつくりと上れば月見草の土手
晩夏の蝶いろいろ一つづつ来るよ
朝顔のひらいて屋根のないところ
状差に秋の団扇があつて部屋
草を踏む犬のはだしも秋めくと
われもこう山の手前に雲のある
鵯のよく鳴くけふの今日限り
秋の薔薇行けばどこまで同じ町
つめたい手おほきな窓に紅葉山
雨樋を石蕗の花へとたどり見る
靴べらの握りが冬の犬の顔
北風の荒れてゐる日の水たまり
寒晴やテトラポッドの脚組み合ふ
ふくらはぎ伸すや日の照る冬の海
石に吹く風の聞こえるかぜぐすり
江ノ島のコップの水や麗らかに
クロッカス団地一棟いま無音
手に水の触れる速さに春の雪
さへづりの向かうに白い村の道
たふれゆく春の夕べのアロエベラ
仔猫野良あけがたなれば慕ひくる
そらまめや雨ふつてゐる窓ひとつ
栗の木が咲いてモルタル壁の家
犬を見るかしこい犬や夏の庭
蒲の穂の先からなほも伸びるもの
サルビヤの町に帽子の若い人
白布のうへ四つの同じ夏料理
冷蔵庫に西日のさしてゐたりけり
秋の山から蠅が来て部屋に入る
バスに見る川をうづめて葛の花
月今宵みづの出てゐる水飲み場
煙草買ふと云うて別れし良夜かな
あの山におほきな岩や紅葉づれる
鳥威なほして今日を終はる人
冷ゆる田と家具工場のありにけり
スケーターズワルツ丘から見る町は
地には霜やさしい人たちの自転車
網フェンスに絡みて枯れてそよ風よ
やすみなく暮れゆく空や毛の帽子
その年は二月に二回雪が降り
↧
↧
落選展2014_3 線路 上田信治
↧
落選展2014_2 こゑ 生駒大祐_テキスト
2 こゑ 生駒大祐
夏雨のあかるさが木に行き渡る
渦の影立ち上りたる泉かな
人呼ばふやうに木を呼ぶ涼しさよ
風鈴の短冊に川流れをり
薔薇の枝の夥しさを座して見る
初夏の口笛で呼ぶ言葉たち
蛭あまたもみあふひとつごころかな
こゑと手といづれやさしき冰水
夏の木のたふれし日差ありにけり
しとやかにあやめの水の古りゆけり
雲甘く嶺を隠しぬ蝸牛
べつとりとあぢさゐ朽ちし茎の色
白鷺の数とほく鳴きかはしけり
真桑瓜みづのかたちをしてゐたり
水鶏見るもはや心のうすみどり
滝殿を覗き込む子や連れてゆく
輪の如き一日が過ぎ烏瓜
色町の音流れゆく秋の川
晴ながら雲の分厚き家居かな
おそろしく真直ぐ秋の日が昇る
絹漉の暗闇にして菌山
製図室ひねもす秋の線引かる
秋草の鞍馬へ取つてかへしけり
抜く釘のおもはぬ若さ雁渡る
木犀の錆び急ぐ夜を何とせむ
鳥のやうに生きて林檎のしぼりみづ
汝と行かむ月のひかりの涸れしかば
ゆふぐれや芦刈りつつも鳩のこゑ
バス寒く窓ごとの青凡そ空
寒林をとほく治めて天さびし
針山の肌の花柄山眠る
ものうげに寒鯉匂ひはじめたり
汝寝ねて夜どほし冬の空があり
降る雪やただ重たさの肥後守
世の中や歩けば蕪とすれちがふ
枯園や音の向かうに落つる水
冬木中一年が身を起こしけり
山茶花に真白き布の被せある
春を待つ水が絵となるときの色
定まりし言葉動かず桜貝
今はなき通草葛もあたたかし
くらがりにゐて鶯を飼ひならす
のぞまれて橋となる木々春のくれ
広がりし桜の枝の届く水
うたごゑの聞こえてとほき彼岸かな
唐代の墨飛び立たばつばくらめ
差し入れて硯濯ぎぬ春の水
我よりも我がこゑ聡しかすみさう
俯せに水は流れて鳥曇
富士低くたやすく春日あたりけり
夏雨のあかるさが木に行き渡る
渦の影立ち上りたる泉かな
人呼ばふやうに木を呼ぶ涼しさよ
風鈴の短冊に川流れをり
薔薇の枝の夥しさを座して見る
初夏の口笛で呼ぶ言葉たち
蛭あまたもみあふひとつごころかな
こゑと手といづれやさしき冰水
夏の木のたふれし日差ありにけり
しとやかにあやめの水の古りゆけり
雲甘く嶺を隠しぬ蝸牛
べつとりとあぢさゐ朽ちし茎の色
白鷺の数とほく鳴きかはしけり
真桑瓜みづのかたちをしてゐたり
水鶏見るもはや心のうすみどり
滝殿を覗き込む子や連れてゆく
輪の如き一日が過ぎ烏瓜
色町の音流れゆく秋の川
晴ながら雲の分厚き家居かな
おそろしく真直ぐ秋の日が昇る
絹漉の暗闇にして菌山
製図室ひねもす秋の線引かる
秋草の鞍馬へ取つてかへしけり
抜く釘のおもはぬ若さ雁渡る
木犀の錆び急ぐ夜を何とせむ
鳥のやうに生きて林檎のしぼりみづ
汝と行かむ月のひかりの涸れしかば
ゆふぐれや芦刈りつつも鳩のこゑ
バス寒く窓ごとの青凡そ空
寒林をとほく治めて天さびし
針山の肌の花柄山眠る
ものうげに寒鯉匂ひはじめたり
汝寝ねて夜どほし冬の空があり
降る雪やただ重たさの肥後守
世の中や歩けば蕪とすれちがふ
枯園や音の向かうに落つる水
冬木中一年が身を起こしけり
山茶花に真白き布の被せある
春を待つ水が絵となるときの色
定まりし言葉動かず桜貝
今はなき通草葛もあたたかし
くらがりにゐて鶯を飼ひならす
のぞまれて橋となる木々春のくれ
広がりし桜の枝の届く水
うたごゑの聞こえてとほき彼岸かな
唐代の墨飛び立たばつばくらめ
差し入れて硯濯ぎぬ春の水
我よりも我がこゑ聡しかすみさう
俯せに水は流れて鳥曇
富士低くたやすく春日あたりけり
↧
落選展2014_2 こゑ 生駒大祐
↧
↧
落選展2014_1 霾のグリエ 赤野四羽_テキスト
1 霾のグリエ 赤野四羽
姥桜花見するひとをみてゐる
未来への河に滴る灰汁の春
軒下に現地集合春の蚊よ
霾のグリエに春闇ジュレ添えて
箱庭にたんぽぽひとつ咲きにけり
春月や高架の下のモンドリアン
雑踏に夜の桜の涼やけき
花曇雀のつがふ螺旋かな
上下左右街を歩かば絵踏かな
春闇に溶けてゆきたるハイソックス
土現る鬼も天使も膏として
理非もなし吾子を守らん春嵐
指の傷いまだ残りて水温む
春光の匂ひをたどる緑かな
死の根っこ掘りかえしたるも花ばかり
海豹や腹を擦りても牙捨てず
山上に蜘蛛の子散りて春疾風
涅槃吹黄色いふうせん西より来
青葉より澄みたる精の飛沫(しぶき)たる
つばくらめ排水管に子を残し
大揚羽地球の端にとまりけり
七色の絵の具溶かして夏の闇
少年が西瓜を抱いて待っている
文学に夏が来れりガルシア=マルケス
修羅場みて胡瓜涼しや絵金祭
麦わらの老婆にふたつ氷菓かな
スタンド・バイ・ミーが真夏をつれてくる
虹の根で跳ねる子見やる日が射した
白物や骸百態夏百夜
夏の砂烟る轍や波高し
瑠璃蜥蜴虹の筆先尻で曳き
コンクリの塀に爪たて蝉の子や
太陽の上に落ちけり田植笠
鰯雲誰も居ぬとびらが閉じる
三日月に暗く膨らむ体育館
魂失せし裁きうつろに鬼灯鳴る
夜歩けば朱き月影たぷたぷと
坂道を下る蜻蛉の高さかな
野分去るパンの耳塩がきいてる
冬鵙や抱き上げし子に脈打てり
切り捨てし大根首に蕾の黄
みすがらに老人を待つ鯨かな
人形よ糸断ち歩め細雪
冬闇に十字切りたる警備員
地の霜をざくざく踏みて役所かな
牡丹雪すずめ垣根にひそみおり
雨宿る鳩の襟元山めぐり
稽古場に天道虫の眠りたる
独楽震え少し迷うて座りこみ
鼻欠けた狛に影揺る初燈
姥桜花見するひとをみてゐる
未来への河に滴る灰汁の春
軒下に現地集合春の蚊よ
霾のグリエに春闇ジュレ添えて
箱庭にたんぽぽひとつ咲きにけり
春月や高架の下のモンドリアン
雑踏に夜の桜の涼やけき
花曇雀のつがふ螺旋かな
上下左右街を歩かば絵踏かな
春闇に溶けてゆきたるハイソックス
土現る鬼も天使も膏として
理非もなし吾子を守らん春嵐
指の傷いまだ残りて水温む
春光の匂ひをたどる緑かな
死の根っこ掘りかえしたるも花ばかり
海豹や腹を擦りても牙捨てず
山上に蜘蛛の子散りて春疾風
涅槃吹黄色いふうせん西より来
青葉より澄みたる精の飛沫(しぶき)たる
つばくらめ排水管に子を残し
大揚羽地球の端にとまりけり
七色の絵の具溶かして夏の闇
少年が西瓜を抱いて待っている
文学に夏が来れりガルシア=マルケス
修羅場みて胡瓜涼しや絵金祭
麦わらの老婆にふたつ氷菓かな
スタンド・バイ・ミーが真夏をつれてくる
虹の根で跳ねる子見やる日が射した
白物や骸百態夏百夜
夏の砂烟る轍や波高し
瑠璃蜥蜴虹の筆先尻で曳き
コンクリの塀に爪たて蝉の子や
太陽の上に落ちけり田植笠
鰯雲誰も居ぬとびらが閉じる
三日月に暗く膨らむ体育館
魂失せし裁きうつろに鬼灯鳴る
夜歩けば朱き月影たぷたぷと
坂道を下る蜻蛉の高さかな
野分去るパンの耳塩がきいてる
冬鵙や抱き上げし子に脈打てり
切り捨てし大根首に蕾の黄
みすがらに老人を待つ鯨かな
人形よ糸断ち歩め細雪
冬闇に十字切りたる警備員
地の霜をざくざく踏みて役所かな
牡丹雪すずめ垣根にひそみおり
雨宿る鳩の襟元山めぐり
稽古場に天道虫の眠りたる
独楽震え少し迷うて座りこみ
鼻欠けた狛に影揺る初燈
↧
落選展2014 1 霾のグリエ 赤野四羽
↧
週刊俳句 第393号 2014年11月2日
第393号
2014年11月2日
■2014落選展 Salon des Refusés
■1 赤野四羽 霾のグリエ
≫読む ≫テキスト
■2 生駒大祐 こゑ
≫読む ≫テキスト
■3 上田信治 線路 *
≫読む ≫テキスト
■4 大中博篤 魂の話
≫読む ≫テキスト
■5 小池康生 最初の雨 *
≫読む ≫テキスト
■6 加藤御影 パズル
≫読む ≫テキスト
■7 栗山麻衣 脱ぎかけ
≫読む ≫テキスト
■8 倉田有希 クレヨン
≫読む ≫テキスト
■9 きしゆみこ 凛凛
≫読む ≫テキスト
■10 工藤定治 徒然
≫読む ≫テキスト
■11 片岡義順 舞ふて舞ふて舞ふてまだまだ枯一葉
≫読む ≫テキスト
■12 さわだかずや ふらんど
≫読む ≫テキスト
■13 杉原祐之 封境
≫読む ≫テキスト
■14 すずきみのる 新機軸
≫読む ≫テキスト
■15 津野利行 室の花
≫読む ≫テキスト
■16 谷口鳥子 バンテージ
≫読む ≫テキスト
■17 高梨 章 空車(むなぐるま)
≫読む ≫テキスト
■18 滝川直広 積木の家 *
≫読む ≫テキスト
■19 中村清潔 仮面
≫読む ≫テキスト
■20 中塚健太 オムレツ
≫読む ≫テキスト
■21 ハードエッジ ゐません
≫読む ≫テキスト
■22 三島ちとせ 弔ひ
≫読む ≫テキスト
■23 前北かおる 菜の花
≫読む ≫テキスト
■24 岬 光世 草の矢
≫読む ≫テキスト
■25 吉川千早 モラトリアムレクイエム
≫読む ≫テキスト
■26 利普苑るな 猫鳴いて
≫読む ≫テキスト
* 予選通過作品
■2014落選展 出展者プロフィール ≫読む
……………………………………………
■〔今週号の表紙〕首都高……西原天気 ≫読む
■後記……上田信治 ≫読む
2014年11月2日
■2014落選展 Salon des Refusés
■1 赤野四羽 霾のグリエ
≫読む ≫テキスト
■2 生駒大祐 こゑ
≫読む ≫テキスト
■3 上田信治 線路 *
≫読む ≫テキスト
■4 大中博篤 魂の話
≫読む ≫テキスト
■5 小池康生 最初の雨 *
≫読む ≫テキスト
■6 加藤御影 パズル
≫読む ≫テキスト
■7 栗山麻衣 脱ぎかけ
≫読む ≫テキスト
■8 倉田有希 クレヨン
≫読む ≫テキスト
■9 きしゆみこ 凛凛
≫読む ≫テキスト
■10 工藤定治 徒然
≫読む ≫テキスト
■11 片岡義順 舞ふて舞ふて舞ふてまだまだ枯一葉
≫読む ≫テキスト
■12 さわだかずや ふらんど
≫読む ≫テキスト
■13 杉原祐之 封境
≫読む ≫テキスト
■14 すずきみのる 新機軸
≫読む ≫テキスト
■15 津野利行 室の花
≫読む ≫テキスト
■16 谷口鳥子 バンテージ
≫読む ≫テキスト
■17 高梨 章 空車(むなぐるま)
≫読む ≫テキスト
■18 滝川直広 積木の家 *
≫読む ≫テキスト
■19 中村清潔 仮面
≫読む ≫テキスト
■20 中塚健太 オムレツ
≫読む ≫テキスト
■21 ハードエッジ ゐません
≫読む ≫テキスト
■22 三島ちとせ 弔ひ
≫読む ≫テキスト
■23 前北かおる 菜の花
≫読む ≫テキスト
■24 岬 光世 草の矢
≫読む ≫テキスト
■25 吉川千早 モラトリアムレクイエム
≫読む ≫テキスト
■26 利普苑るな 猫鳴いて
≫読む ≫テキスト
* 予選通過作品
■2014落選展 出展者プロフィール ≫読む
……………………………………………
■〔今週号の表紙〕首都高……西原天気 ≫読む
■後記……上田信治 ≫読む
↧
後記+プロフィール394
後記 ● 西原天気
落選展、まだまだ続きます。
≫http://weekly-haiku.blogspot.jp/2014/11/3932014112.html
感想など、お気軽にコメントください。
●
ウラハイで小津夜景さんの俳句シリーズ「みみず・ぶっくす」がスタート。
≫こちらです
お楽しみください。
●
東京西郊に住んでいて、都心に出かけることはそう頻繁ではないのですが、たまに銀座に出たときには、ビゴというパン屋さん(デパートの地下にあります)に立ち寄ったりします。ここのパンがとてもおいしい。
おいしいパンは、おいしいごはんの次くらいに、人を幸せにしますね。
と、こんな話をするのは、小誌を「パン屋」にたとえてくれた人がいるからです。
ちょっと良く言い過ぎ(笑。たまに、まずいパンも置いてあったりすると思うのですが、いつ行っても開いているパン屋ではあるわけです。
いずれにせよ、こんなふうに言っていただけるのは、ありがたいことです。
●
それではまた、次の日曜日にお会いしましょう。
no.392/2014-10-26 profile
■秋尾 敏 あきお・びん
昭和25年、埼玉県生まれ。軸主宰、全国俳誌協会会長、千葉県現代俳句協会副会長兼幹事長、千葉県俳句作家協会理事長。「西日本新聞」選者。短詩文化学会事務局長、俳文学会会員。評論『子規の近代』等、句集『悪の種』等。
■九里順子 くのり・じゅんこ
1962年福井県大野市生れ。宮城学院女子大学学芸学部教授。「里」同人。著書『明治詩史論――透谷・羽衣・敏を視座として――』(和泉書院・2006年)『室生犀星の詩法』(翰林書房・2013年)句集『静物』(邑書林・2013年)
■小津夜景 おづ・やけい
1973年生まれ。無所属。
■関悦史 せき・えつし
1969年、茨城生まれ。第1回芝不器男俳句新人賞城戸朱理奨励賞、第11回俳句界評論賞受賞。「豈」同人。共著『新撰21』(邑書林)。句集『六十億本の回転する曲がつた棒』(2011)にて第3回田中裕明賞を受賞。URL:http://etushinoheya.web.
■橋本 直 はしもと・すなお
1967年生。「豈」同人、「鬼」会員。「俳句の創作と研究のホームページ」
■大塚 凱 おおつか・がい
1995年千葉県生まれ。俳句甲子園第14、15、16回大会出場。「群青 」同人。
■松本てふこ まつもと・てふこ 1981年生まれ。2000年、作句開始。2004年「童子」入会。同年「新童賞」受賞。『新撰21』『超新撰21』(邑書林)に小論で参加。アンソロジー『俳コレ』に入集100句。2012年「童子賞」受賞。「童子」同人。
■瀬戸正洋 せと・せいよう
1954年生まれ。れもん二十歳代俳句研究会に途中参加。春燈「第三次桃青会」結成に参加。月刊俳句同人誌「里」創刊に参加。2014年『俳句と雑文 B』を上梓。
■トオイダイスケ とおい・だいすけ
1982年栃木県佐野市生まれ。東京都在住。澤俳句会所属。
URL: http://daisuketoi.com Twitter: @daisuketoi
■大井さち子 おおい・さちこ
1960年生まれ。長野県在住。「鷹」同人。句集「秋の椅子」(2009年邑書林)。
■太田うさぎ おおた・うさぎ
1963年東京生まれ。「豆の木」「雷魚」会員。現代俳句協会会員。共著に『俳コレ』(2011年、邑書林)。
■馬場古戸暢 ばば・ことのぶ
1983年生まれ。自由律俳句(随句)結社「草原」同人。
■西原天気 さいばら・てんき
1955年生まれ。「月天」同人。句集に『人名句集チャーリーさん』(2005年・私家版)、『けむり』(2011年10月・西田書店)。ブログ「俳句的日常」 twitter
●
落選展、まだまだ続きます。
≫http://weekly-haiku.blogspot.jp/2014/11/3932014112.html
感想など、お気軽にコメントください。
●
ウラハイで小津夜景さんの俳句シリーズ「みみず・ぶっくす」がスタート。
≫こちらです
お楽しみください。
●
東京西郊に住んでいて、都心に出かけることはそう頻繁ではないのですが、たまに銀座に出たときには、ビゴというパン屋さん(デパートの地下にあります)に立ち寄ったりします。ここのパンがとてもおいしい。
おいしいパンは、おいしいごはんの次くらいに、人を幸せにしますね。
と、こんな話をするのは、小誌を「パン屋」にたとえてくれた人がいるからです。
某所で書いたけれど週刊俳句は美味しいパン屋さんみたいだ。美味しいバケットにサンドウィッチ。たまにわけわからない創作パン。焼きたてのパンの良い匂いがしてくる。そういうお店にはつい立ち寄りたくなる。晴れの日も雨の日も。
— ふじみん (@fd_m_n) 2014, 11月 7ちょっと良く言い過ぎ(笑。たまに、まずいパンも置いてあったりすると思うのですが、いつ行っても開いているパン屋ではあるわけです。
いずれにせよ、こんなふうに言っていただけるのは、ありがたいことです。
●
それではまた、次の日曜日にお会いしましょう。
no.392/2014-10-26 profile
■秋尾 敏 あきお・びん
昭和25年、埼玉県生まれ。軸主宰、全国俳誌協会会長、千葉県現代俳句協会副会長兼幹事長、千葉県俳句作家協会理事長。「西日本新聞」選者。短詩文化学会事務局長、俳文学会会員。評論『子規の近代』等、句集『悪の種』等。
■九里順子 くのり・じゅんこ
1962年福井県大野市生れ。宮城学院女子大学学芸学部教授。「里」同人。著書『明治詩史論――透谷・羽衣・敏を視座として――』(和泉書院・2006年)『室生犀星の詩法』(翰林書房・2013年)句集『静物』(邑書林・2013年)
■小津夜景 おづ・やけい
1973年生まれ。無所属。
■関悦史 せき・えつし
1969年、茨城生まれ。第1回芝不器男俳句新人賞城戸朱理奨励賞、第11回俳句界評論賞受賞。「豈」同人。共著『新撰21』(邑書林)。句集『六十億本の回転する曲がつた棒』(2011)にて第3回田中裕明賞を受賞。URL:http://etushinoheya.web.
■橋本 直 はしもと・すなお
1967年生。「豈」同人、「鬼」会員。「俳句の創作と研究のホームページ」
■大塚 凱 おおつか・がい
1995年千葉県生まれ。俳句甲子園第14、15、16回大会出場。「群青 」同人。
■松本てふこ まつもと・てふこ 1981年生まれ。2000年、作句開始。2004年「童子」入会。同年「新童賞」受賞。『新撰21』『超新撰21』(邑書林)に小論で参加。アンソロジー『俳コレ』に入集100句。2012年「童子賞」受賞。「童子」同人。
■瀬戸正洋 せと・せいよう
1954年生まれ。れもん二十歳代俳句研究会に途中参加。春燈「第三次桃青会」結成に参加。月刊俳句同人誌「里」創刊に参加。2014年『俳句と雑文 B』を上梓。
■トオイダイスケ とおい・だいすけ
1982年栃木県佐野市生まれ。東京都在住。澤俳句会所属。
URL: http://daisuketoi.com Twitter: @daisuketoi
■大井さち子 おおい・さちこ
1960年生まれ。長野県在住。「鷹」同人。句集「秋の椅子」(2009年邑書林)。
■太田うさぎ おおた・うさぎ
1963年東京生まれ。「豆の木」「雷魚」会員。現代俳句協会会員。共著に『俳コレ』(2011年、邑書林)。
■馬場古戸暢 ばば・ことのぶ
1983年生まれ。自由律俳句(随句)結社「草原」同人。
■西原天気 さいばら・てんき
1955年生まれ。「月天」同人。句集に『人名句集チャーリーさん』(2005年・私家版)、『けむり』(2011年10月・西田書店)。ブログ「俳句的日常」 twitter
●
↧
↧
自由律俳句を読む 67 中塚唯人〔1〕 馬場古戸暢
自由律俳句を読む 67 中塚唯人〔1〕
馬場古戸暢
馬場古戸暢
中塚唯人(なかつかただと、1949-)は、東京出身の自由律俳人。1993年、父檀急逝のため、中塚一碧楼、檀と続いた自由律俳句誌「海紅」の三代目社主となる。東京自由律俳句会、自由律句のひろば、世界俳句協会に所属するなど、様々な活動を続けている。以下では、数句を選んで鑑賞したい。
春の蛇口からこぼれ出たさくら 中塚唯人
公園の水道の蛇口に、さくらの花びらが詰まっていたのだろうか。あるいは、春という季節の比喩か。陽気な雰囲気が伝わってくる。
ゴギブリの夏にシュッと一吹きしてしまいました 同
ゴキブリ退治系の商品の宣伝に用いられそうである。
いいわけみつけられず夏の陽は暮れる 同
日暮れるまでいいわけを探していたのだろう。素直に謝るしかない。
きっちり揃えたスリッパにも秋の日暮れる 同
誰かの家の廊下の様子を詠んだものとみた。家主の性格は、こういうところにあらわれるものなのである。
銀杏一つ二つと拾い今年もやっぱり三百六十五日 同
年の瀬らしい句。閏年が四年に一度あるはずだが、どうにも忘れていってしまう。
↧
〔今週号の表紙〕第394号 ブルーのインク 西原天気
〔今週号の表紙〕
第394号 ブルーのインク
西原天気
青インクの青にはじつにさまざまな青があります。銘柄によってメーカーによって。
青いインクで書いた手紙をいただいて、その色を「なんて感じのいい青だろう!」と気に入ってしまうことがあります。書いた人に「どのインクなんですか?」と聞いてみたくてしかたがなくなりますが、そういうわけにも行きません。
それに紙によっても発色が微妙に異なるので、同じインクを手に入れたからといって、自分が惚れた青になるとは限りません。「隣の芝生は青い」のたぐいで、「他人の書いた青はキレイ」なのです。
●
週俳ではトップ写真を募集しています。詳細は≫こちら
第394号 ブルーのインク
西原天気
青インクの青にはじつにさまざまな青があります。銘柄によってメーカーによって。
青いインクで書いた手紙をいただいて、その色を「なんて感じのいい青だろう!」と気に入ってしまうことがあります。書いた人に「どのインクなんですか?」と聞いてみたくてしかたがなくなりますが、そういうわけにも行きません。
それに紙によっても発色が微妙に異なるので、同じインクを手に入れたからといって、自分が惚れた青になるとは限りません。「隣の芝生は青い」のたぐいで、「他人の書いた青はキレイ」なのです。
●
週俳ではトップ写真を募集しています。詳細は≫こちら
↧
【週俳10月の俳句を読む】私はYAKUZA Ⅶ 瀬戸正洋
【週俳10月の俳句を読む】
私はYAKUZA Ⅶ
瀬戸正洋
ジョツキを凍らせ、25度の甲類焼酎も冷やし、ホッピーも冷やす。ジョツキには目盛があり、そこまで焼酎を注ぐ、あとはホッピーを注げば出来上がる。これを「三冷」という。氷を入れてはいけないのだ。だが、「三冷」を実践している店は驚くほど少ない。だから、ホッピーは自宅で飲むに限る。そんな、ほろ酔い加減で「私はYAKUZA Ⅶ」を書いている。不謹慎ななどと思ってはいけない。人は必ず何かに酔っている。何かに酔っていなければ、書くことも、生きていくこともできないのだから。
紅葉するさくら卵の中の街 福田若之
さくらの木の紅葉、あまり美しいとは思わない。さらに、落葉を掃除することを考えるとうんざりしてしまう。卵の中に街がある。その街は殻で守られていて繁栄している。但し、閉塞感のある街だと思う。
団地の芝生がざりがに臭い秋の風 福田若之
ざりがに臭い芝生の上を秋風が通り過ぎる。ざりがにの臭いと秋風が交じり合ったのである。背景には、それほど高くない古ぼけた団地の連棟が見える。
露の世の鼻を交換する工事 福田若之
はかない世の中だから鼻を交換するのだという。そして、鼻を交換することを工事だという。鼻を交換することで、何か、すこしぐらいは良くなるのではないかなどと思ったりしている。
愛憎の虎が歩道橋に銀河 福田若之
愛憎とは同じ人に対し誰もが思う感情である。愛が深ければ憎しみは増し、愛がそれほどでもなければ憎しみもそれほどではない。その相手が人ではなく虎なのである。それも歩道橋にいるのだ。作者は、どれほど深く虎を愛しているのだろうか、何のために、全てを賭けて虎を憎んでいるのだろうか。仰ぎ見れば都会の空に銀河。
こおろぎを轢いた地下鉄同士の会話 福田若之
轢かれたこおろぎが落ちている。複数、落ちている。それを轢いたのは地下鉄であり、その地下鉄同士が会話をしているという。私鉄やJRのように空の下を走るのではなく、加害者には地下を走る電車が相応しいのかも知れない。「地下鉄同士の会話」とイメージできた時、死んだこおろぎに気が付いたことに、作者は感謝したに違いない。
電柱の努力で満月のはやい 福田若之
努力とはよい言葉だ。月が出たのは、それも満月のはやく出たのは、電柱の努力によるものなのである。もしかしたら、天空を満月が円盤のようにはやく動いているのかも知れない。もちろん、何もかもが電柱のご努力によってなのだ。
原子力空母をコスモスが覆う 福田若之
コスモスの咲く丘の向こうに東京湾が見える。亜米利加の原子力空母が横須賀基地に入ろうとしているのだろう。遠近法を使い原子力空母がコスモスに覆われているような情景にした。この方法は、弱者が強者に対抗するひとつの手段なのである。
ところで、強者のように振舞っている人はどこにでもいるが、その誰もが本心を隠している。生きるということは、淋しくて悲しくて、孤独なことなのである。もしかしたら、遠近法とは弱者が病んだ社会に対し対抗する手段なのかも知れない。
秋の虹電話線上の暴動 福田若之
秋の虹を電話線が妨げている。作者は秋の虹の全てを眺めたいのだ。その不快感の原因を秋の虹であるとした。好かれている人から暴動などと言われても秋の虹は困るだろう。秋の虹に原因があるとしたことは言いがかりなのである。作者が立つ位置を工夫すればいいだけの話なのである。
林檎A落ちて林檎Bは昇る 福田若之
JAの林檎の出荷場を想像した。林檎を選別しているのだ。Aは規格外、Bは規格内。そして、林檎を洗浄し磨く。洗浄機の中で林檎は上下に動いている。私といえば、おそらく「林檎A」であり選別され落とされ割れてしまう運命にあるのだろう。確かに、私は、誰からも選ばれるような生き方はしていない。
むむむむといわしぐも舌長い人 福田若之
いわしぐもの下に人がいる。いわしぐもは、「むむむむ」としいて、人の舌は長い。ただ、それだけのことなのだが、「いわしぐも」と「舌長い人」が、何故か面白いし、食い意地の張っている私は、その長い舌でいわしぐもを食べてみたいなどと思ってしまう。野原に寝転んでいると、雲は、それなりに美味そうなかたちをしていると思ったりもする。
手も足も届かない椅子秋日和 二村典子
座ったまま椅子を動かそうとしたら手が届かない。足に引っ掛けようとしたがそれも難しい。秋の良く晴れた日であった。
水澄むや澄めば澄むほど遠ざかる 二村典子
汚れていた方が暮らしやすいということだ。欲しいものでさえも遠ざかってしまう。とかく世間とはそういうものなのである。美し過ぎると邪心がうしろから近付いて来て悪さを仕掛ける。汚れることは生きていくために必要なことだと言われれば、身も心も汚れきっている私は、心の底から安堵し、今宵も、旨い酒が飲めるのである。
天高し行きと帰りは違う靴 二村典子
私にとって靴は履き心地が良く疲れなければ、それで十分なのである。駅ビルにも郊外にも靴の量販店はいくらでもある。靴を買う時、履いていった靴は処分してもらうことにしている。捨てる手間が省けるし、靴が増えることもないからだ。季節は秋、履き替えたあとの爽やかな気持ちで私は珈琲店に入る。
銀杏を割る難題を聞き入れる 二村典子
銀杏を割るにはコツがいるし、心乱されることなく難題を聞くためにはコツも必要である。しかしながら、それを会得してしまえば、それはその人にとって難題を聞くことも苦痛ではなくなるのだ。
台風がまた来る週末三連休 二村典子
作者にとって体育の日が絡んだ三連休は、何らかの思い入れがあるのだろう。忘れてはいけない何かがあったのである。俳句作品とは、他人が読むためのものではなく、あくまでも自分が読むためのものなのである。既に他人となってしまった過去の自分を、現在の自分が読むためのものなのである。
ねじの谷から虫の声ねじ山へ 二村典子
ねじの山がある。その中にコオロギか何かが入り込んで鳴いているのだ。ねじの谷から聞こえていた虫の声がねじの山から聞こえるようになったとは、移動したのではなく鳴いたり鳴き止んだりしている。そんな状況を、このように表現したのである。
今日の月息子の同級生がいる 二村典子
仲秋の名月、傍らには息子の同級生がいた。その時、息子は、そこに居たのか居なかったのかは不明である。息子の同級生は男性なのか女性なのかも不明である。だが、このことは詮索する必要はないのだ。不明のままにしておくことの方が面白いのだ。作者は息子の同級生がいることに気付いた。ただ、それだけのことなのである。
こころ。から。くはへた。秋。の。茄子である。 佐山哲郎
これは、作品ではなく題名である。だが、これも作品と同じく17音であり季語もある。句読点を使い遊んでいることも同じだ。これらの作品は、お経なのである。お経だから、本人には意味がある。だが、お経なのだから、読み手(聞き手)には心地良い文字(音楽)であり、句読点も含めた言葉のオブジェなのである。
星、色の。さかな。くはへて霧の、猫。 佐山哲郎
猫がさかなを咥えて飛び出したのである。だが、そのさかなは「星、色」であり、咥えた猫はただの猫ではなく「霧の猫」なのである。
振って、いま。野菊の。墓。へ。葬らん。 佐山哲郎
「野菊の墓」は、伊藤左千夫の小説である。悲しく淡い恋のものがたりである。政夫が民子を「振って、今。」なのだろうか。小説では、野菊の好きだった民子の墓の回りに野菊を植えたのだが、この作品は反対なのである。そのへんのところが「振って、いま。」を考える切っ掛けになるのかも知れない。
触るな、の。早良親王。秋、旱。 佐山哲郎
作者は「早良親王のことが好きだ」と言っている。早良親王には、「秋、旱。」が似合うのかも知れない。
反対に、触らぬ神に祟り無しだと思ってみる。臆病者の私は、どんなちっぽけなことでも、祟られることだけはご免被りたいのだ。それには、目立ってはいけない。人知れず、うつむいて、静かに暮すのだ。生きている人間に祟られることほど厄介なことはないと思う。
月。田毎。やや。あたかも。と。いふ、副詞。 佐山哲郎
棚田に月が映っている。作者はそれを、「やや」「あたかも」という副詞で表現した。「すこしばかり」あるいは「さながら」という意味である。姥捨の棚田も有名である。ほろ酔い気分で、この文字の塊をいくら眺めても、月光の降り注ぐ棚田しか見えてこない。それでいいのだと思う。
そういえば、神奈川県は西の外れ、某城お堀端の近くに「田毎」という蕎麦屋がある。こんな風景を眺めながら、蕎麦味噌を舐め熱燗というのも悪くはないと思う。
あ、秋。海。雨。ワイパーの、変な音。 佐山哲郎
海までのドライブ。季節は秋である。雨が降ってきた。ワイパーを動かすと調子が悪く変な音がしている。助手席に座っているのは愛人なのだ。ワイパーが壊れるのは、そんな時だと決まっている。もうひとつ、はじまりが「あ、」なのだから、絶対、愛人なのである。
あんた、皺。それ干柿。の、やうな、それ。 佐山哲郎
これは、老人の会話である。会話を作品にしたのである。句読点が一番生きている作品のような気がする。その上に、干し柿は甘くて美味しいのである。
私が子供の頃、縁側に皮を剝いた柿が簾のように干されていた。現在、そんなことをする家は見かけなくなった。老人が干し柿を作らなくなったのだ。手間をかけずに美味しいものがいくらでも食べることのできる時代になったということなのだろう。
できちやつた婚。の。夜長。の。已然形。 佐山哲郎
已然形がこのドラマを象徴している。「できちやつた婚」には無数のストーリーがあるし、私のような老人にとっては、絶対に経験することのできない世界なのである。「できちやつた婚」ができちゃつたら、私は、法律によって罰せられるのである。
啄木鳥、の。自傷行為。を。疑はず。 佐山哲郎
啄木鳥に自傷行為があるのかないのか私は、知らない。ただ、人間には間違いなくある。私は、啄木の歌集「悲しき玩具」を思い出したりしている。石川啄木には、「我等の一団と彼」という作品が残ってはいるが、彼は、本当は、小説が書きたかったのである。
秋。遺影。イエイ。を。叫ぶ。だれですか。 佐山哲郎
六十歳を越えると人生は「秋」なのだという。(既に、真冬なのだろうと私は思うが)そろそろ、「遺影」用の写真のことを考えるべき年頃なのである。そして、思わず「イエイ」と叫ぶのである。もちろん、これは洒落である。誰ですかなどと気取って尋ねる必要などないのである。叫んでいるのは本人に決まっているし、叫ばれているのも本人なのだから。
遺影用。写真。撮りつこ。する。花野。 佐山哲郎
花野で遺影用の写真を撮りっこするのは三十歳代の夫婦であって欲しい。子育ての真っ最中、ふと、そんな気持ちになることがあっても当然だと思う。
でも、佐山さんと、そのお友達のことだから、大勢のお爺さんお婆さん同士が、けらけらと笑いながら遺影用の写真の撮り合いつこをしているのだろう。「イエイ」などと言ったりして。
雁や竹垣すこしづつ緩び 大西朋
竹垣がすこしづつ緩んできているという。竹垣は、緩むことはないのだが雁を眺めていたらそんな気持ちになってきたのだ。
鵙の贄音なき雨の大粒に 大西朋
鵙の贄が枝に刺さっている。雨が降っている。だんだん大粒になってきたが雨音はしない。子供の頃、鵙の巣を見つけたり、鵙の贄を見つけたりした記憶が蘇ってきた。
鬼の子の揺れていささか眠きかな 大西朋
鬼の子が揺れているのは日陰である。蓑から出ている棒状の先の一点がどこかにくっ付いている。従って、揺れているのはくっ付いている細い枝なのである。枝と鬼の子が揺れているのを眺めた作者は、揺りかごのようだと思い、いささか眠くなったのである。
秋高し薬缶と如雨露並べ置き 塩見明子
薬缶と如雨露を並べて置いたのだが理由がわからない。理由なんてどうでもいいじゃないかと作者は言っているのだろう。たとえば、それは、家庭菜園のための如雨露、その如雨露に水を補給するための薬缶。少し離れたところに、その菜園はあるのだ。それにしても「秋高し」とはいい言葉だ。
虫の音や消しゴムに角なくなりて 塩見明子
使い込んだ消しゴムがノオトの傍らにある。いまどき、鉛筆と消しゴムなどというと郷愁を誘う。窓の外より虫の音が聞こえる。使い込んだ鉛筆とノオトと消しゴム。そして、虫の音、作者は当然のようにやさしさにつつまれている。
鳥渡る食堂の窓開け放ち 塩見明子
海辺にある働く人たちが主として利用する食堂のような気がする。窓は開け放たれていて爽やかな海風が入ってくる。窓から空を見上げれば南の島に向う渡り鳥の群れが見える。どこかからやって来た根無し草の旅人が飯を食べていたりして。女将さんは亭主の自慢話などしていたりして。
改札をはさみて話す秋彼岸 塩見明子
春と秋のお彼岸にしか会えないのだから話すことはいくらでもあるのだろう。駅員や乗降客がいてもお構いなしだ。深刻な話ではなく、どうでもいい世間話なのである。ホームの土手には曼珠沙華が咲いている。
蔦紅葉皿に平たくライス来て 塩見明子
壁には蔦紅葉、それがレストランの中に居ても見えるのだ。ライスが皿に盛られて運ばれて来た。思ったよりも平らに盛られていることに気付いた。消費税が3%上がったからなのかなどと思ってはいけない。それなりに工夫された盛り付けなのである。昼間のビールはことのほか美味しい。
いわしぐも駅から次の駅が見ゆ 越智友亮
これは間違いなく都会の駅である。田舎では、こんな近くに駅を作るというような無駄なことはしない。近ければ歩けばいいのである。都会の駅のホームで秋を感じるのは、ふと、見上げた空に、鰯雲を見つけたときぐらいなのかも知れない。
虫しぐれ眠くても手紙を書くよ 越智友亮
これは間違いなく愛する人に手紙を書いているのである。それも、虫しぐれの中で。「眠くても手紙を書くよ」とは相手に訴えているのだが、心で訴えているに過ぎない。行間を読むなどというが、作者のあまえているようなやさしさは、他の綴られた言葉の端々から必ず伝わるものなのである。だが、伝わった方が良いのか悪いのかは別の話だとは思うが。
ひとを待つすすきと自動販売機 越智友亮
ローカル線の無人駅の駅舎の前、あるいは、田舎のバスの停留所の前に一台の自動販売機がある。その傍らにはすすきが風に揺れている。作者は人を待っているのだ。さて、「すすき」と自動販売機、いったい作者はどんな人を待っているのだろうか。
カップ酒あたため秋の星明るし 越智友亮
カップ酒を温めるとは、それを湯の中に入れるのだろう。しばらくして、湯から取り出し蓋を外し口に含む。ほっと一息、これが、また、たまらないのだ。ふと、見上げると、夜空が、いつもより明るく感じられた。秋だからなどと思う。今日は、何故か不思議に穏やかな一日であった。
ホッピーの話からはじまりカップ酒の作品で終わる。私にとっても穏やかな休日であった。自己を抑制することのほとんどできない私にとって、酒は危険この上ない液体なのである。酒神に守られているというのは自分で思っているに過ぎないのなのかも知れない。飲み過ぎるから人に嫌われ、食べ過ぎるから体重が増加する。
デルポイのアポロンの神殿に奉納された碑文「汝自身を知れ」「度を越すなかれ」は、馬鹿な私にとって身に詰まされる言葉だとつくづく思うのである。壁に貼り、毎日、唱える価値は十分過ぎるほどある。
また、一週間が始まる。往復4時間掛けて会社へ通うのである。サラリーマンにとって幸福な日とは、休日の前日と給料日である。不幸な時といえば休日の午後十時あたりか。身も心も貧しいのだから意気がる必要もなく、明日からの金儲けのために、少しでも眠る時間を確保しようなどと思っている。
第389号 2014年10月5日
■福田若之 紙粘土の港 10句 ≫読む
第390号 2014年10月12日
■二村典子 違う靴 10句 ≫読む
第391号 2014年10月19日
■佐山哲郎 こころ。から。くはへた。秋。の。茄子である。 10句 ≫読む
■大西 朋 青鷹 10句 ≫読む
第392号 2014年10月26日
■塩見明子 改札 10句 ≫読む
■越智友亮 暗 10句 ≫読む
私はYAKUZA Ⅶ
瀬戸正洋
ジョツキを凍らせ、25度の甲類焼酎も冷やし、ホッピーも冷やす。ジョツキには目盛があり、そこまで焼酎を注ぐ、あとはホッピーを注げば出来上がる。これを「三冷」という。氷を入れてはいけないのだ。だが、「三冷」を実践している店は驚くほど少ない。だから、ホッピーは自宅で飲むに限る。そんな、ほろ酔い加減で「私はYAKUZA Ⅶ」を書いている。不謹慎ななどと思ってはいけない。人は必ず何かに酔っている。何かに酔っていなければ、書くことも、生きていくこともできないのだから。
紅葉するさくら卵の中の街 福田若之
さくらの木の紅葉、あまり美しいとは思わない。さらに、落葉を掃除することを考えるとうんざりしてしまう。卵の中に街がある。その街は殻で守られていて繁栄している。但し、閉塞感のある街だと思う。
団地の芝生がざりがに臭い秋の風 福田若之
ざりがに臭い芝生の上を秋風が通り過ぎる。ざりがにの臭いと秋風が交じり合ったのである。背景には、それほど高くない古ぼけた団地の連棟が見える。
露の世の鼻を交換する工事 福田若之
はかない世の中だから鼻を交換するのだという。そして、鼻を交換することを工事だという。鼻を交換することで、何か、すこしぐらいは良くなるのではないかなどと思ったりしている。
愛憎の虎が歩道橋に銀河 福田若之
愛憎とは同じ人に対し誰もが思う感情である。愛が深ければ憎しみは増し、愛がそれほどでもなければ憎しみもそれほどではない。その相手が人ではなく虎なのである。それも歩道橋にいるのだ。作者は、どれほど深く虎を愛しているのだろうか、何のために、全てを賭けて虎を憎んでいるのだろうか。仰ぎ見れば都会の空に銀河。
こおろぎを轢いた地下鉄同士の会話 福田若之
轢かれたこおろぎが落ちている。複数、落ちている。それを轢いたのは地下鉄であり、その地下鉄同士が会話をしているという。私鉄やJRのように空の下を走るのではなく、加害者には地下を走る電車が相応しいのかも知れない。「地下鉄同士の会話」とイメージできた時、死んだこおろぎに気が付いたことに、作者は感謝したに違いない。
電柱の努力で満月のはやい 福田若之
努力とはよい言葉だ。月が出たのは、それも満月のはやく出たのは、電柱の努力によるものなのである。もしかしたら、天空を満月が円盤のようにはやく動いているのかも知れない。もちろん、何もかもが電柱のご努力によってなのだ。
原子力空母をコスモスが覆う 福田若之
コスモスの咲く丘の向こうに東京湾が見える。亜米利加の原子力空母が横須賀基地に入ろうとしているのだろう。遠近法を使い原子力空母がコスモスに覆われているような情景にした。この方法は、弱者が強者に対抗するひとつの手段なのである。
ところで、強者のように振舞っている人はどこにでもいるが、その誰もが本心を隠している。生きるということは、淋しくて悲しくて、孤独なことなのである。もしかしたら、遠近法とは弱者が病んだ社会に対し対抗する手段なのかも知れない。
秋の虹電話線上の暴動 福田若之
秋の虹を電話線が妨げている。作者は秋の虹の全てを眺めたいのだ。その不快感の原因を秋の虹であるとした。好かれている人から暴動などと言われても秋の虹は困るだろう。秋の虹に原因があるとしたことは言いがかりなのである。作者が立つ位置を工夫すればいいだけの話なのである。
林檎A落ちて林檎Bは昇る 福田若之
JAの林檎の出荷場を想像した。林檎を選別しているのだ。Aは規格外、Bは規格内。そして、林檎を洗浄し磨く。洗浄機の中で林檎は上下に動いている。私といえば、おそらく「林檎A」であり選別され落とされ割れてしまう運命にあるのだろう。確かに、私は、誰からも選ばれるような生き方はしていない。
むむむむといわしぐも舌長い人 福田若之
いわしぐもの下に人がいる。いわしぐもは、「むむむむ」としいて、人の舌は長い。ただ、それだけのことなのだが、「いわしぐも」と「舌長い人」が、何故か面白いし、食い意地の張っている私は、その長い舌でいわしぐもを食べてみたいなどと思ってしまう。野原に寝転んでいると、雲は、それなりに美味そうなかたちをしていると思ったりもする。
手も足も届かない椅子秋日和 二村典子
座ったまま椅子を動かそうとしたら手が届かない。足に引っ掛けようとしたがそれも難しい。秋の良く晴れた日であった。
水澄むや澄めば澄むほど遠ざかる 二村典子
汚れていた方が暮らしやすいということだ。欲しいものでさえも遠ざかってしまう。とかく世間とはそういうものなのである。美し過ぎると邪心がうしろから近付いて来て悪さを仕掛ける。汚れることは生きていくために必要なことだと言われれば、身も心も汚れきっている私は、心の底から安堵し、今宵も、旨い酒が飲めるのである。
天高し行きと帰りは違う靴 二村典子
私にとって靴は履き心地が良く疲れなければ、それで十分なのである。駅ビルにも郊外にも靴の量販店はいくらでもある。靴を買う時、履いていった靴は処分してもらうことにしている。捨てる手間が省けるし、靴が増えることもないからだ。季節は秋、履き替えたあとの爽やかな気持ちで私は珈琲店に入る。
銀杏を割る難題を聞き入れる 二村典子
銀杏を割るにはコツがいるし、心乱されることなく難題を聞くためにはコツも必要である。しかしながら、それを会得してしまえば、それはその人にとって難題を聞くことも苦痛ではなくなるのだ。
台風がまた来る週末三連休 二村典子
作者にとって体育の日が絡んだ三連休は、何らかの思い入れがあるのだろう。忘れてはいけない何かがあったのである。俳句作品とは、他人が読むためのものではなく、あくまでも自分が読むためのものなのである。既に他人となってしまった過去の自分を、現在の自分が読むためのものなのである。
ねじの谷から虫の声ねじ山へ 二村典子
ねじの山がある。その中にコオロギか何かが入り込んで鳴いているのだ。ねじの谷から聞こえていた虫の声がねじの山から聞こえるようになったとは、移動したのではなく鳴いたり鳴き止んだりしている。そんな状況を、このように表現したのである。
今日の月息子の同級生がいる 二村典子
仲秋の名月、傍らには息子の同級生がいた。その時、息子は、そこに居たのか居なかったのかは不明である。息子の同級生は男性なのか女性なのかも不明である。だが、このことは詮索する必要はないのだ。不明のままにしておくことの方が面白いのだ。作者は息子の同級生がいることに気付いた。ただ、それだけのことなのである。
こころ。から。くはへた。秋。の。茄子である。 佐山哲郎
これは、作品ではなく題名である。だが、これも作品と同じく17音であり季語もある。句読点を使い遊んでいることも同じだ。これらの作品は、お経なのである。お経だから、本人には意味がある。だが、お経なのだから、読み手(聞き手)には心地良い文字(音楽)であり、句読点も含めた言葉のオブジェなのである。
星、色の。さかな。くはへて霧の、猫。 佐山哲郎
猫がさかなを咥えて飛び出したのである。だが、そのさかなは「星、色」であり、咥えた猫はただの猫ではなく「霧の猫」なのである。
振って、いま。野菊の。墓。へ。葬らん。 佐山哲郎
「野菊の墓」は、伊藤左千夫の小説である。悲しく淡い恋のものがたりである。政夫が民子を「振って、今。」なのだろうか。小説では、野菊の好きだった民子の墓の回りに野菊を植えたのだが、この作品は反対なのである。そのへんのところが「振って、いま。」を考える切っ掛けになるのかも知れない。
触るな、の。早良親王。秋、旱。 佐山哲郎
作者は「早良親王のことが好きだ」と言っている。早良親王には、「秋、旱。」が似合うのかも知れない。
反対に、触らぬ神に祟り無しだと思ってみる。臆病者の私は、どんなちっぽけなことでも、祟られることだけはご免被りたいのだ。それには、目立ってはいけない。人知れず、うつむいて、静かに暮すのだ。生きている人間に祟られることほど厄介なことはないと思う。
月。田毎。やや。あたかも。と。いふ、副詞。 佐山哲郎
棚田に月が映っている。作者はそれを、「やや」「あたかも」という副詞で表現した。「すこしばかり」あるいは「さながら」という意味である。姥捨の棚田も有名である。ほろ酔い気分で、この文字の塊をいくら眺めても、月光の降り注ぐ棚田しか見えてこない。それでいいのだと思う。
そういえば、神奈川県は西の外れ、某城お堀端の近くに「田毎」という蕎麦屋がある。こんな風景を眺めながら、蕎麦味噌を舐め熱燗というのも悪くはないと思う。
あ、秋。海。雨。ワイパーの、変な音。 佐山哲郎
海までのドライブ。季節は秋である。雨が降ってきた。ワイパーを動かすと調子が悪く変な音がしている。助手席に座っているのは愛人なのだ。ワイパーが壊れるのは、そんな時だと決まっている。もうひとつ、はじまりが「あ、」なのだから、絶対、愛人なのである。
あんた、皺。それ干柿。の、やうな、それ。 佐山哲郎
これは、老人の会話である。会話を作品にしたのである。句読点が一番生きている作品のような気がする。その上に、干し柿は甘くて美味しいのである。
私が子供の頃、縁側に皮を剝いた柿が簾のように干されていた。現在、そんなことをする家は見かけなくなった。老人が干し柿を作らなくなったのだ。手間をかけずに美味しいものがいくらでも食べることのできる時代になったということなのだろう。
できちやつた婚。の。夜長。の。已然形。 佐山哲郎
已然形がこのドラマを象徴している。「できちやつた婚」には無数のストーリーがあるし、私のような老人にとっては、絶対に経験することのできない世界なのである。「できちやつた婚」ができちゃつたら、私は、法律によって罰せられるのである。
啄木鳥、の。自傷行為。を。疑はず。 佐山哲郎
啄木鳥に自傷行為があるのかないのか私は、知らない。ただ、人間には間違いなくある。私は、啄木の歌集「悲しき玩具」を思い出したりしている。石川啄木には、「我等の一団と彼」という作品が残ってはいるが、彼は、本当は、小説が書きたかったのである。
秋。遺影。イエイ。を。叫ぶ。だれですか。 佐山哲郎
六十歳を越えると人生は「秋」なのだという。(既に、真冬なのだろうと私は思うが)そろそろ、「遺影」用の写真のことを考えるべき年頃なのである。そして、思わず「イエイ」と叫ぶのである。もちろん、これは洒落である。誰ですかなどと気取って尋ねる必要などないのである。叫んでいるのは本人に決まっているし、叫ばれているのも本人なのだから。
遺影用。写真。撮りつこ。する。花野。 佐山哲郎
花野で遺影用の写真を撮りっこするのは三十歳代の夫婦であって欲しい。子育ての真っ最中、ふと、そんな気持ちになることがあっても当然だと思う。
でも、佐山さんと、そのお友達のことだから、大勢のお爺さんお婆さん同士が、けらけらと笑いながら遺影用の写真の撮り合いつこをしているのだろう。「イエイ」などと言ったりして。
雁や竹垣すこしづつ緩び 大西朋
竹垣がすこしづつ緩んできているという。竹垣は、緩むことはないのだが雁を眺めていたらそんな気持ちになってきたのだ。
鵙の贄音なき雨の大粒に 大西朋
鵙の贄が枝に刺さっている。雨が降っている。だんだん大粒になってきたが雨音はしない。子供の頃、鵙の巣を見つけたり、鵙の贄を見つけたりした記憶が蘇ってきた。
鬼の子の揺れていささか眠きかな 大西朋
鬼の子が揺れているのは日陰である。蓑から出ている棒状の先の一点がどこかにくっ付いている。従って、揺れているのはくっ付いている細い枝なのである。枝と鬼の子が揺れているのを眺めた作者は、揺りかごのようだと思い、いささか眠くなったのである。
秋高し薬缶と如雨露並べ置き 塩見明子
薬缶と如雨露を並べて置いたのだが理由がわからない。理由なんてどうでもいいじゃないかと作者は言っているのだろう。たとえば、それは、家庭菜園のための如雨露、その如雨露に水を補給するための薬缶。少し離れたところに、その菜園はあるのだ。それにしても「秋高し」とはいい言葉だ。
虫の音や消しゴムに角なくなりて 塩見明子
使い込んだ消しゴムがノオトの傍らにある。いまどき、鉛筆と消しゴムなどというと郷愁を誘う。窓の外より虫の音が聞こえる。使い込んだ鉛筆とノオトと消しゴム。そして、虫の音、作者は当然のようにやさしさにつつまれている。
鳥渡る食堂の窓開け放ち 塩見明子
海辺にある働く人たちが主として利用する食堂のような気がする。窓は開け放たれていて爽やかな海風が入ってくる。窓から空を見上げれば南の島に向う渡り鳥の群れが見える。どこかからやって来た根無し草の旅人が飯を食べていたりして。女将さんは亭主の自慢話などしていたりして。
改札をはさみて話す秋彼岸 塩見明子
春と秋のお彼岸にしか会えないのだから話すことはいくらでもあるのだろう。駅員や乗降客がいてもお構いなしだ。深刻な話ではなく、どうでもいい世間話なのである。ホームの土手には曼珠沙華が咲いている。
蔦紅葉皿に平たくライス来て 塩見明子
壁には蔦紅葉、それがレストランの中に居ても見えるのだ。ライスが皿に盛られて運ばれて来た。思ったよりも平らに盛られていることに気付いた。消費税が3%上がったからなのかなどと思ってはいけない。それなりに工夫された盛り付けなのである。昼間のビールはことのほか美味しい。
いわしぐも駅から次の駅が見ゆ 越智友亮
これは間違いなく都会の駅である。田舎では、こんな近くに駅を作るというような無駄なことはしない。近ければ歩けばいいのである。都会の駅のホームで秋を感じるのは、ふと、見上げた空に、鰯雲を見つけたときぐらいなのかも知れない。
虫しぐれ眠くても手紙を書くよ 越智友亮
これは間違いなく愛する人に手紙を書いているのである。それも、虫しぐれの中で。「眠くても手紙を書くよ」とは相手に訴えているのだが、心で訴えているに過ぎない。行間を読むなどというが、作者のあまえているようなやさしさは、他の綴られた言葉の端々から必ず伝わるものなのである。だが、伝わった方が良いのか悪いのかは別の話だとは思うが。
ひとを待つすすきと自動販売機 越智友亮
ローカル線の無人駅の駅舎の前、あるいは、田舎のバスの停留所の前に一台の自動販売機がある。その傍らにはすすきが風に揺れている。作者は人を待っているのだ。さて、「すすき」と自動販売機、いったい作者はどんな人を待っているのだろうか。
カップ酒あたため秋の星明るし 越智友亮
カップ酒を温めるとは、それを湯の中に入れるのだろう。しばらくして、湯から取り出し蓋を外し口に含む。ほっと一息、これが、また、たまらないのだ。ふと、見上げると、夜空が、いつもより明るく感じられた。秋だからなどと思う。今日は、何故か不思議に穏やかな一日であった。
ホッピーの話からはじまりカップ酒の作品で終わる。私にとっても穏やかな休日であった。自己を抑制することのほとんどできない私にとって、酒は危険この上ない液体なのである。酒神に守られているというのは自分で思っているに過ぎないのなのかも知れない。飲み過ぎるから人に嫌われ、食べ過ぎるから体重が増加する。
デルポイのアポロンの神殿に奉納された碑文「汝自身を知れ」「度を越すなかれ」は、馬鹿な私にとって身に詰まされる言葉だとつくづく思うのである。壁に貼り、毎日、唱える価値は十分過ぎるほどある。
また、一週間が始まる。往復4時間掛けて会社へ通うのである。サラリーマンにとって幸福な日とは、休日の前日と給料日である。不幸な時といえば休日の午後十時あたりか。身も心も貧しいのだから意気がる必要もなく、明日からの金儲けのために、少しでも眠る時間を確保しようなどと思っている。
第389号 2014年10月5日
■福田若之 紙粘土の港 10句 ≫読む
第390号 2014年10月12日
■二村典子 違う靴 10句 ≫読む
第391号 2014年10月19日
■佐山哲郎 こころ。から。くはへた。秋。の。茄子である。 10句 ≫読む
■大西 朋 青鷹 10句 ≫読む
第392号 2014年10月26日
■塩見明子 改札 10句 ≫読む
■越智友亮 暗 10句 ≫読む
↧
【週俳10月の俳句を読む】それぞれの武器 松本てふこ
【週俳10月の俳句を読む】
それぞれの武器
松本てふこ
久々にこのコーナーにお邪魔する。
蔦紅葉皿に平たくライス来て 塩見明子
作者と十年以上前に何回か超結社の句会で同席する機会があった。抑制のきいた表現と嫌みの無い取り合わせのセンスを武器に、句会で高得点を得ていた。その後、総合誌の選考で何回かその名前を目にしていたが、活字で作品をきちんと読んだのは久しぶりだった。彼女はすでに得ていた武器をより確固たるものにしていた。
ひとを待つすすきと自動販売機 越智友亮
子規の忌の座りて傘を股間へと
越智友亮の句が放つイノセントな輝きは多少の世間との軋轢を経ても失われるものではなかったようだ。「ひとを待つ」とベタな擬人化を用いて一句に仕立てたり、「股間」という言葉をけろりと使ったり。
諧謔のフィールドに真顔で切り込んでいく姿勢はやっぱり私淑するイケスミ流なのかな、と思ったりも。
『新撰21』の出版記念パーティーなどで学生時代の彼に会うと、俳句を存分に楽しんでいる姿が眩しくて眩しくて本当にうらやましくて羨望がねじれるあまり「はやく社会人になって仕事と俳句の両立に苦労しなよ……!!!!!!」と思ってしまっていたことをここに懺悔したく思う。ごめんなさい、お互い頑張ろう!(私はいま無職ですけど)
こおろぎを轢いた地下鉄同士の会話 福田若之
越智の句からは人間くささや人懐かしさを感じるが、彼とほぼ同世代の福田の句からは今回、親しげに読者をすり寄らせる感情から作品をなるべく遠ざけようという操作を強く感じた。
当季の句ではあるが全ての句はフィクションめいており(虎が歩道橋にはいないだろう、という景そのもののフィクション性ではなくて)彼の持ち味である(と私が思い込んでいた)形式の中で固有名詞と戯れる無邪気さも、口語体で切り込んでくるインパクトもなく、とにかくひどく注意深く「何も語ろうとしないように」「何も描こうとしないように」ずらされた言葉たちが彼の作品として並んでいた。
天高し行きと帰りは違う靴 二村典子
私事で恐縮だが、先日、この句のような旅をした。行きはパンプスを履いて、帰りはスニーカー。実に、かさばる。全く愉快ではない。途中で雨にも降られ、終始どんより気分であった。私の旅と対照的に、この句はとても愉快そうである。季語が天高しだからだろうか、何からも自由な気分が伝わる。中七下五は軽やかさのあまり靴を脱いで踊り出しそうな勢いがあって、可笑しい。
雨に森けぶりはじめし青鷹 大西朋
地に足を付けてものを見なければ抒情も不可能なのだ、という気持ちにさせられる十句であった。まず読解する、そして景を思い描いて、イメージを膨らませる。例えば爽波の句だったりすると、じっくり読まないで処理するように読んでいくとトランス状態のような気分を味わえて楽しい、という面もあるので一概には言えないが、一瞬のことを詠んでいるからといって早急に読んでは駄目なのだ。お前は俳句を読むプロセスを踏めているのか? と自らに問いかけながら読む、貴重な時間だった。
遺影用。写真。撮りつこ。する。花野。 佐山哲郎
死や痛みを近くに感じていればいるほど彼らにとって花野は美しいものである。その広さ、明るさ、生きているものを近くに感じられること、誰かと一緒にふざけられること、全てが彼らをなぐさめる。だからこそ、互いの死の予行演習として遺影を撮りあいもするのだろう。句点が彼らの笑い声のようにちりばめられている。
第389号 2014年10月5日
■福田若之 紙粘土の港 10句 ≫読む
第390号 2014年10月12日
■二村典子 違う靴 10句 ≫読む
第391号 2014年10月19日
■佐山哲郎 こころ。から。くはへた。秋。の。茄子である。 10句 ≫読む
■大西 朋 青鷹 10句 ≫読む
第392号 2014年10月26日
■塩見明子 改札 10句 ≫読む
■越智友亮 暗 10句 ≫読む
それぞれの武器
松本てふこ
久々にこのコーナーにお邪魔する。
蔦紅葉皿に平たくライス来て 塩見明子
作者と十年以上前に何回か超結社の句会で同席する機会があった。抑制のきいた表現と嫌みの無い取り合わせのセンスを武器に、句会で高得点を得ていた。その後、総合誌の選考で何回かその名前を目にしていたが、活字で作品をきちんと読んだのは久しぶりだった。彼女はすでに得ていた武器をより確固たるものにしていた。
ひとを待つすすきと自動販売機 越智友亮
子規の忌の座りて傘を股間へと
越智友亮の句が放つイノセントな輝きは多少の世間との軋轢を経ても失われるものではなかったようだ。「ひとを待つ」とベタな擬人化を用いて一句に仕立てたり、「股間」という言葉をけろりと使ったり。
諧謔のフィールドに真顔で切り込んでいく姿勢はやっぱり私淑するイケスミ流なのかな、と思ったりも。
『新撰21』の出版記念パーティーなどで学生時代の彼に会うと、俳句を存分に楽しんでいる姿が眩しくて眩しくて本当にうらやましくて羨望がねじれるあまり「はやく社会人になって仕事と俳句の両立に苦労しなよ……!!!!!!」と思ってしまっていたことをここに懺悔したく思う。ごめんなさい、お互い頑張ろう!(私はいま無職ですけど)
こおろぎを轢いた地下鉄同士の会話 福田若之
越智の句からは人間くささや人懐かしさを感じるが、彼とほぼ同世代の福田の句からは今回、親しげに読者をすり寄らせる感情から作品をなるべく遠ざけようという操作を強く感じた。
当季の句ではあるが全ての句はフィクションめいており(虎が歩道橋にはいないだろう、という景そのもののフィクション性ではなくて)彼の持ち味である(と私が思い込んでいた)形式の中で固有名詞と戯れる無邪気さも、口語体で切り込んでくるインパクトもなく、とにかくひどく注意深く「何も語ろうとしないように」「何も描こうとしないように」ずらされた言葉たちが彼の作品として並んでいた。
天高し行きと帰りは違う靴 二村典子
私事で恐縮だが、先日、この句のような旅をした。行きはパンプスを履いて、帰りはスニーカー。実に、かさばる。全く愉快ではない。途中で雨にも降られ、終始どんより気分であった。私の旅と対照的に、この句はとても愉快そうである。季語が天高しだからだろうか、何からも自由な気分が伝わる。中七下五は軽やかさのあまり靴を脱いで踊り出しそうな勢いがあって、可笑しい。
雨に森けぶりはじめし青鷹 大西朋
地に足を付けてものを見なければ抒情も不可能なのだ、という気持ちにさせられる十句であった。まず読解する、そして景を思い描いて、イメージを膨らませる。例えば爽波の句だったりすると、じっくり読まないで処理するように読んでいくとトランス状態のような気分を味わえて楽しい、という面もあるので一概には言えないが、一瞬のことを詠んでいるからといって早急に読んでは駄目なのだ。お前は俳句を読むプロセスを踏めているのか? と自らに問いかけながら読む、貴重な時間だった。
遺影用。写真。撮りつこ。する。花野。 佐山哲郎
死や痛みを近くに感じていればいるほど彼らにとって花野は美しいものである。その広さ、明るさ、生きているものを近くに感じられること、誰かと一緒にふざけられること、全てが彼らをなぐさめる。だからこそ、互いの死の予行演習として遺影を撮りあいもするのだろう。句点が彼らの笑い声のようにちりばめられている。
第389号 2014年10月5日
■福田若之 紙粘土の港 10句 ≫読む
第390号 2014年10月12日
■二村典子 違う靴 10句 ≫読む
第391号 2014年10月19日
■佐山哲郎 こころ。から。くはへた。秋。の。茄子である。 10句 ≫読む
■大西 朋 青鷹 10句 ≫読む
第392号 2014年10月26日
■塩見明子 改札 10句 ≫読む
■越智友亮 暗 10句 ≫読む
↧
↧
【週俳10月の俳句を読む】秋から、冬へ トオイダイスケ
【週俳10月の俳句を読む】
秋から、冬へ
トオイダイスケ
俳句を始めて二度目の冬を迎えて、俳句を読むたのしみは、感情を動かされることではなく感覚を動かされることだ、とまだわずかだが実感を持って言 えるようになってきた気がしている。もしくは、感覚を動かされることによって感情がわずかに波立つこと、だろうか。もっと強く実感を持ってそう言 い切れるようになりたい。
電柱の努力で満月のはやい 福田若之
「電柱」は無数に立てられていて、電力を運ぶための電線をつないでいる。「電柱の努力」は、そんな電柱そのものの努力とも言えるが、「電柱である かのような、無数無名のつなぎ合わされて支えあっている努力」とも読める。
それによって満月が「はやい」。月、それも満月は古来じっくり眺めて楽しむものとされてきた気がするが、そんなことは一切構わないかのようだ。し かもひらがなで言い捨てられたような速さ(早さ)は、身体を躍動させる歓びの感触がまるでない。「はやい」満月は、デジタルデータとしての写真に 写されたもののような感触を残す。
どの言葉もあえて軽く、「絆」とか「がんばろう」みたいに、ぱっと聞いた美しさで思考を停止させるように人を縛る言葉としてあえて使われて一句を 成しているように見えて、読んだ感触が今生活していてよく見たり聞いたりする言葉や雰囲気のようで、現実味のある句だと思った。
実は実は秋の重さよ実は実は 二村典子
上五は「みはじつは」、下五は「じつはみは」と読んだ。視覚(字面)と聴覚(声に出して読んだ印象)とで、「秋の重さ」をその軽みをも含めて味わ えた句。
あ、秋。海。雨。ワイパーの、変な音。 佐山哲郎
「あ」「あき」「うみ」「あめ」の、句読点を挟んだゆったりとしたたたみかけが、あ行やま行の音の重なりも相まって、澄んでいてかつみずみずし い、広々とした空間の中での多層感をもたらす。そこに「ワイパーの」斜めの動きと、「変な音」が、意識を狭い視覚と聴覚に誘導する。
また繰り返して頭から読むと、フロントガラスのワイパーで拭かれた部分が再びゆっくり濡れていくような感じがしてくる。実は自動車の中にいたの か、外にいたのか分からなくなるような感じもしてきて、多層感がどんどん増してくる。
雨に森けぶりはじめし青鷹 大西朋
「もろがえり」という言葉を恥ずかしながら初めて知ったが、この句は「青」の字がとても美しくみずみずしく味わえる句だな、と思った。
蔦紅葉皿に平たくライス来て 塩見明子
落ち着いた古い洋食屋だろうか。「皿」に「平たく」盛られた「ライス」は、「ご飯」の「和の物」としての安心感を残しつつ、それが表層的に「洋の 物」という無邪気な憧れとしてそのまま味わえるようになるうれしさがある。そのうれしさとご飯こと「ライス」の輝きが「来る」。明治大正昭和的な 郷愁を実感する、その実感を懐かしむような句でもあって、「電柱の~」と真逆の方向と真逆の濃密さとで、同じような強度がある。
子規の忌の座りて傘を股間へと 越智友亮
座って傘を股間に置くのはおそらく電車の車内でだろう。傘は何度か払われたがまだうっすらと濡れていて、それを挟んで倒れないように、弱い力で支 えている膝の内側は衣服ごしに少しづつ湿っていく(みずみずしさ、とは程遠く)。たぶん遅い夜、終電車の、たくさん人が降りる駅を過ぎて、終着駅 に近づいているところに思える。ある一人の一日の「仕事」の終わりが感じられてきて(またそれは、さっきまで電車に乗っていた大勢の人一人ひとり の「仕事」の終わり、という多層感のある)、安堵を伴った寂しさとほの寒さとがある。かつ「子規」が格闘した江戸明治、その延長の大正昭和の「モ ダン」感への郷愁を伴ったエネルギッシュな気配が去っていく予感がある。雨の――わずかなみずみずしさの――残る冬のはじまりを思う。
第389号 2014年10月5日
■福田若之 紙粘土の港 10句 ≫読む
第390号 2014年10月12日
■二村典子 違う靴 10句 ≫読む
第391号 2014年10月19日
■佐山哲郎 こころ。から。くはへた。秋。の。茄子である。 10句 ≫読む
■大西 朋 青鷹 10句 ≫読む
第392号 2014年10月26日
■塩見明子 改札 10句 ≫読む
■越智友亮 暗 10句 ≫読む
秋から、冬へ
トオイダイスケ
俳句を始めて二度目の冬を迎えて、俳句を読むたのしみは、感情を動かされることではなく感覚を動かされることだ、とまだわずかだが実感を持って言 えるようになってきた気がしている。もしくは、感覚を動かされることによって感情がわずかに波立つこと、だろうか。もっと強く実感を持ってそう言 い切れるようになりたい。
電柱の努力で満月のはやい 福田若之
「電柱」は無数に立てられていて、電力を運ぶための電線をつないでいる。「電柱の努力」は、そんな電柱そのものの努力とも言えるが、「電柱である かのような、無数無名のつなぎ合わされて支えあっている努力」とも読める。
それによって満月が「はやい」。月、それも満月は古来じっくり眺めて楽しむものとされてきた気がするが、そんなことは一切構わないかのようだ。し かもひらがなで言い捨てられたような速さ(早さ)は、身体を躍動させる歓びの感触がまるでない。「はやい」満月は、デジタルデータとしての写真に 写されたもののような感触を残す。
どの言葉もあえて軽く、「絆」とか「がんばろう」みたいに、ぱっと聞いた美しさで思考を停止させるように人を縛る言葉としてあえて使われて一句を 成しているように見えて、読んだ感触が今生活していてよく見たり聞いたりする言葉や雰囲気のようで、現実味のある句だと思った。
実は実は秋の重さよ実は実は 二村典子
上五は「みはじつは」、下五は「じつはみは」と読んだ。視覚(字面)と聴覚(声に出して読んだ印象)とで、「秋の重さ」をその軽みをも含めて味わ えた句。
あ、秋。海。雨。ワイパーの、変な音。 佐山哲郎
「あ」「あき」「うみ」「あめ」の、句読点を挟んだゆったりとしたたたみかけが、あ行やま行の音の重なりも相まって、澄んでいてかつみずみずし い、広々とした空間の中での多層感をもたらす。そこに「ワイパーの」斜めの動きと、「変な音」が、意識を狭い視覚と聴覚に誘導する。
また繰り返して頭から読むと、フロントガラスのワイパーで拭かれた部分が再びゆっくり濡れていくような感じがしてくる。実は自動車の中にいたの か、外にいたのか分からなくなるような感じもしてきて、多層感がどんどん増してくる。
雨に森けぶりはじめし青鷹 大西朋
「もろがえり」という言葉を恥ずかしながら初めて知ったが、この句は「青」の字がとても美しくみずみずしく味わえる句だな、と思った。
蔦紅葉皿に平たくライス来て 塩見明子
落ち着いた古い洋食屋だろうか。「皿」に「平たく」盛られた「ライス」は、「ご飯」の「和の物」としての安心感を残しつつ、それが表層的に「洋の 物」という無邪気な憧れとしてそのまま味わえるようになるうれしさがある。そのうれしさとご飯こと「ライス」の輝きが「来る」。明治大正昭和的な 郷愁を実感する、その実感を懐かしむような句でもあって、「電柱の~」と真逆の方向と真逆の濃密さとで、同じような強度がある。
子規の忌の座りて傘を股間へと 越智友亮
座って傘を股間に置くのはおそらく電車の車内でだろう。傘は何度か払われたがまだうっすらと濡れていて、それを挟んで倒れないように、弱い力で支 えている膝の内側は衣服ごしに少しづつ湿っていく(みずみずしさ、とは程遠く)。たぶん遅い夜、終電車の、たくさん人が降りる駅を過ぎて、終着駅 に近づいているところに思える。ある一人の一日の「仕事」の終わりが感じられてきて(またそれは、さっきまで電車に乗っていた大勢の人一人ひとり の「仕事」の終わり、という多層感のある)、安堵を伴った寂しさとほの寒さとがある。かつ「子規」が格闘した江戸明治、その延長の大正昭和の「モ ダン」感への郷愁を伴ったエネルギッシュな気配が去っていく予感がある。雨の――わずかなみずみずしさの――残る冬のはじまりを思う。
第389号 2014年10月5日
■福田若之 紙粘土の港 10句 ≫読む
第390号 2014年10月12日
■二村典子 違う靴 10句 ≫読む
第391号 2014年10月19日
■佐山哲郎 こころ。から。くはへた。秋。の。茄子である。 10句 ≫読む
■大西 朋 青鷹 10句 ≫読む
第392号 2014年10月26日
■塩見明子 改札 10句 ≫読む
■越智友亮 暗 10句 ≫読む
↧
【週俳10月の俳句を読む】切なさがむやみに 大井さち子
【週俳10月の俳句を読む】
切なさがむやみに
大井さち子
太陽と月を引つ張り烏瓜 大西 朋
烏瓜は夏の夜、レースに縁どられたような白い花を咲かせる。そして秋にはウリ坊のような艶やかな縞模様の実となり、冬が近づくころに赤く色付き、辺りの枯色の中で途方に暮れたようにポツンとぶら下がっている。
作者はこの烏瓜が太陽と月を引っ張っていると言う。烏瓜が引っ張るというのはどういうことなのだろう。太陽と月の運行は烏瓜が司っているというのだろうか。
やじろべえのように烏瓜を中心にして均衡を保っているのではない。例えば凧上げを想像してみたらどうか。強い風を味方にして凧はグングン空高く上がってゆく。凧の糸はピーンと張ってまるで空と自分がつながったかのように感じる瞬間。
そう、空に太陽と月を上げているのは烏瓜なのだ。
水澄むや澄めば澄むほど遠ざかる 二村典子
何から遠ざかるのだろう。いや、何から何が遠ざかるのだろう。
水澄む秋の美しい空気の中、「澄めば澄むほど遠ざかる」という措辞は胸をぎゅっと掴まれるような切なさがある。
具体的なものを何も見せない分、読む者の切なさがむやみに増す一句である。
第389号 2014年10月5日
■福田若之 紙粘土の港 10句 ≫読む
第390号 2014年10月12日
■二村典子 違う靴 10句 ≫読む
第391号 2014年10月19日
■佐山哲郎 こころ。から。くはへた。秋。の。茄子である。 10句 ≫読む
■大西 朋 青鷹 10句 ≫読む
第392号 2014年10月26日
■塩見明子 改札 10句 ≫読む■越智友亮 暗 10句 ≫読む
切なさがむやみに
大井さち子
太陽と月を引つ張り烏瓜 大西 朋
烏瓜は夏の夜、レースに縁どられたような白い花を咲かせる。そして秋にはウリ坊のような艶やかな縞模様の実となり、冬が近づくころに赤く色付き、辺りの枯色の中で途方に暮れたようにポツンとぶら下がっている。
作者はこの烏瓜が太陽と月を引っ張っていると言う。烏瓜が引っ張るというのはどういうことなのだろう。太陽と月の運行は烏瓜が司っているというのだろうか。
やじろべえのように烏瓜を中心にして均衡を保っているのではない。例えば凧上げを想像してみたらどうか。強い風を味方にして凧はグングン空高く上がってゆく。凧の糸はピーンと張ってまるで空と自分がつながったかのように感じる瞬間。
そう、空に太陽と月を上げているのは烏瓜なのだ。
水澄むや澄めば澄むほど遠ざかる 二村典子
何から遠ざかるのだろう。いや、何から何が遠ざかるのだろう。
水澄む秋の美しい空気の中、「澄めば澄むほど遠ざかる」という措辞は胸をぎゅっと掴まれるような切なさがある。
具体的なものを何も見せない分、読む者の切なさがむやみに増す一句である。
第389号 2014年10月5日
■福田若之 紙粘土の港 10句 ≫読む
第390号 2014年10月12日
■二村典子 違う靴 10句 ≫読む
第391号 2014年10月19日
■佐山哲郎 こころ。から。くはへた。秋。の。茄子である。 10句 ≫読む
■大西 朋 青鷹 10句 ≫読む
第392号 2014年10月26日
■塩見明子 改札 10句 ≫読む■越智友亮 暗 10句 ≫読む
↧
【週俳10月の俳句を読む】独断を描く 大塚凱
【週俳10月の俳句を読む】
独断を描く
大塚 凱
蔦紅葉皿に平たくライス来て 塩見明子
個人的な話でお恥ずかしい限りだが、今年になって漸く学生服を脱いだ私に、先日はじめて中村屋のカレーを食べる機会が訪れた。最も驚いたのは、ライスが雪の厚さで皿に盛られていることであった。普段口にする、半ば丼飯のようなカレーとは一線を画している。掲句、「ライス来て」の表現はやや強引と言えなくもないが、どのような店で、どのような食事をしているのかが目に浮かぶのである。「蔦紅葉」がその風景の想起を支えている、たおやかな一句である。
この句が「描く」ことによって成り立っている一方で、次の句は作者が対象を「捉える」ことに面白さがある。
雁や竹垣すこしづつ緩び 大西 朋
東北地方の農村風景を思うだろうか。自ら訪れたことがないので恐縮だが、このような竹垣はあるような気がする。「竹垣」が「すこしづつ緩」ぶという感覚の鋭さ、その時間的スケールの広がりが、「雁」の空間的スケールと共鳴している。と同時に、雁の変わらぬ営みと、滅びゆく竹垣の対比も鮮やかである。
そして、「捉える」ということはつまり「独断」とも言い換えられる。それが魅力的か否かが、即ち一句の生死を意味する。
啄木鳥、の。自傷行為。を。疑はず。 佐山哲郎
木をつつく。啄木鳥の習性を「自傷行為」と捉えたのは面白い独断である。ここに描かれている啄木鳥は盲目的、あるいは狂信的ですらあるのだ。そして、句読点を多用した文体も、非常に興味深い。五・七・五のリズムを踏まえながらも句読点を用いて四・一・六・一・五の破調を半ば強引に導入することで、啄木鳥の有り様を音韻からも表現している。この連作については、次週、詳しく取り上げたい。
ひとを待つすすきと自動販売機 越智友亮
同連作のうち、〈いわしぐも駅から次の駅が見ゆ〉〈暗渠いづれおほきなかはや秋のくれ〉〈彼岸花みんなが傘を差すので差す〉にも惹かれた。いずれも、抒情的な匂いの季語と現代性を取り合わせた魅力がある。
掲句は「すすき」が「ひとを待つ」だけではやや曖昧なドグマになるところを、「自動販売機」が「ひとを待つ」という逆転の発想と接着させたところで一句になっている。それは「すすき」のへりに「自動販売機」が立っている人気のない県道沿い、のような風景をめいめいに想起させてくれるからである。それこそ、彼らの待人は風のようにやって来るのであろう。
そして、ときに「独断」は独断的に構成された情景として「描写」される。
原子力空母をコスモスが覆ふ 福田若之
「紙粘土の港」は10句を通し、俳句の文脈でシュルレアリスムを実践する試みが感じられる。中でも掲句はその試みが最も成功している。「原子力空母」という我々の日常生活から遠く危うい存在が、「コスモス」により幻想性へと昇華された。そして、その二物が「覆ふ」という動詞で斡旋されることにより、読者は超現実としての景を描くことができるのである。その点で、この句は10句の連作中で最も絵画的・色彩的だ。それはなによりも、句の言葉に過度な負荷がかかっていない、平易な表現で構成されていることに支えられている。表現手法としてのシュルレアリスムが難解な傾向にあるとするならば、句の言葉自体は一層平易でなければ共感を得るのは困難な宿命にあるのではないか。
第389号 2014年10月5日
■福田若之 紙粘土の港 10句 ≫読む
第390号 2014年10月12日
■二村典子 違う靴 10句 ≫読む
第391号 2014年10月19日
■佐山哲郎 こころ。から。くはへた。秋。の。茄子である。 10句 ≫読む
■大西 朋 青鷹 10句 ≫読む
第392号 2014年10月26日
■塩見明子 改札 10句 ≫読む■越智友亮 暗 10句 ≫読む
独断を描く
大塚 凱
蔦紅葉皿に平たくライス来て 塩見明子
個人的な話でお恥ずかしい限りだが、今年になって漸く学生服を脱いだ私に、先日はじめて中村屋のカレーを食べる機会が訪れた。最も驚いたのは、ライスが雪の厚さで皿に盛られていることであった。普段口にする、半ば丼飯のようなカレーとは一線を画している。掲句、「ライス来て」の表現はやや強引と言えなくもないが、どのような店で、どのような食事をしているのかが目に浮かぶのである。「蔦紅葉」がその風景の想起を支えている、たおやかな一句である。
この句が「描く」ことによって成り立っている一方で、次の句は作者が対象を「捉える」ことに面白さがある。
雁や竹垣すこしづつ緩び 大西 朋
東北地方の農村風景を思うだろうか。自ら訪れたことがないので恐縮だが、このような竹垣はあるような気がする。「竹垣」が「すこしづつ緩」ぶという感覚の鋭さ、その時間的スケールの広がりが、「雁」の空間的スケールと共鳴している。と同時に、雁の変わらぬ営みと、滅びゆく竹垣の対比も鮮やかである。
そして、「捉える」ということはつまり「独断」とも言い換えられる。それが魅力的か否かが、即ち一句の生死を意味する。
啄木鳥、の。自傷行為。を。疑はず。 佐山哲郎
木をつつく。啄木鳥の習性を「自傷行為」と捉えたのは面白い独断である。ここに描かれている啄木鳥は盲目的、あるいは狂信的ですらあるのだ。そして、句読点を多用した文体も、非常に興味深い。五・七・五のリズムを踏まえながらも句読点を用いて四・一・六・一・五の破調を半ば強引に導入することで、啄木鳥の有り様を音韻からも表現している。この連作については、次週、詳しく取り上げたい。
ひとを待つすすきと自動販売機 越智友亮
同連作のうち、〈いわしぐも駅から次の駅が見ゆ〉〈暗渠いづれおほきなかはや秋のくれ〉〈彼岸花みんなが傘を差すので差す〉にも惹かれた。いずれも、抒情的な匂いの季語と現代性を取り合わせた魅力がある。
掲句は「すすき」が「ひとを待つ」だけではやや曖昧なドグマになるところを、「自動販売機」が「ひとを待つ」という逆転の発想と接着させたところで一句になっている。それは「すすき」のへりに「自動販売機」が立っている人気のない県道沿い、のような風景をめいめいに想起させてくれるからである。それこそ、彼らの待人は風のようにやって来るのであろう。
そして、ときに「独断」は独断的に構成された情景として「描写」される。
原子力空母をコスモスが覆ふ 福田若之
「紙粘土の港」は10句を通し、俳句の文脈でシュルレアリスムを実践する試みが感じられる。中でも掲句はその試みが最も成功している。「原子力空母」という我々の日常生活から遠く危うい存在が、「コスモス」により幻想性へと昇華された。そして、その二物が「覆ふ」という動詞で斡旋されることにより、読者は超現実としての景を描くことができるのである。その点で、この句は10句の連作中で最も絵画的・色彩的だ。それはなによりも、句の言葉に過度な負荷がかかっていない、平易な表現で構成されていることに支えられている。表現手法としてのシュルレアリスムが難解な傾向にあるとするならば、句の言葉自体は一層平易でなければ共感を得るのは困難な宿命にあるのではないか。
第389号 2014年10月5日
■福田若之 紙粘土の港 10句 ≫読む
第390号 2014年10月12日
■二村典子 違う靴 10句 ≫読む
第391号 2014年10月19日
■佐山哲郎 こころ。から。くはへた。秋。の。茄子である。 10句 ≫読む
■大西 朋 青鷹 10句 ≫読む
第392号 2014年10月26日
■塩見明子 改札 10句 ≫読む■越智友亮 暗 10句 ≫読む
↧
【八田木枯の一句】水は澄み鳥はまるごと翔んでをり 太田うさぎ
【八田木枯の一句】
水は澄み鳥はまるごと翔んでをり
太田うさぎ
そんなふうに詠まれちまったら凡夫はこの先どうすりゃいいのサ、と歯噛みしたくなる句がある。その一つが、
水は澄み鳥はまるごと翔んでをり 八田木枯 (鏡騒)
秋、それとなく見上げた空に鳥の姿を認めると思い出す。
つまりは鳥が飛んでいる、それだけしか言っていないのだ。まるごと翔んでいる。当たり前である。まるごと以外に飛び様があろうか。欠けながら飛ぶ鳥がいるとしたらそれは魑魅魍魎の類か、おおかたは眼科に診てもらった方がいいのである。
ところが、だ。何だろう、この鳥の実在性は。「まるごと」と詠まれることで、羽毛の下に肉と血とを漲らせた確たる一個としての質感が眼前に迫ってくるだけでなく、個体を越えた“鳥というもの“の本質が差し出されているように思えるのだ。
上空に鳥の羽ばたく一方、地を統べるのは澄みきった水だ。水は澄み/鳥は翔び、という対句法が静寂と運動のコントラストを際立たせて句の地平を限りなく広げていく。
芸、というと小手先のテクニックを弄するかのごとく聞こえるかもしれないが、敢えて芸達者な句だと言いたい。「まるごと」の把握は半可通には出来ない。大技を決めておきながらしれっと何にも言っていないような顔をしている。実際何も言っていないじゃないか。いや、そこが凄いところなんだ。と空に向かってため息をつく。どうにもニクいのである。
水は澄み鳥はまるごと翔んでをり
太田うさぎ
そんなふうに詠まれちまったら凡夫はこの先どうすりゃいいのサ、と歯噛みしたくなる句がある。その一つが、
水は澄み鳥はまるごと翔んでをり 八田木枯 (鏡騒)
秋、それとなく見上げた空に鳥の姿を認めると思い出す。
つまりは鳥が飛んでいる、それだけしか言っていないのだ。まるごと翔んでいる。当たり前である。まるごと以外に飛び様があろうか。欠けながら飛ぶ鳥がいるとしたらそれは魑魅魍魎の類か、おおかたは眼科に診てもらった方がいいのである。
ところが、だ。何だろう、この鳥の実在性は。「まるごと」と詠まれることで、羽毛の下に肉と血とを漲らせた確たる一個としての質感が眼前に迫ってくるだけでなく、個体を越えた“鳥というもの“の本質が差し出されているように思えるのだ。
上空に鳥の羽ばたく一方、地を統べるのは澄みきった水だ。水は澄み/鳥は翔び、という対句法が静寂と運動のコントラストを際立たせて句の地平を限りなく広げていく。
芸、というと小手先のテクニックを弄するかのごとく聞こえるかもしれないが、敢えて芸達者な句だと言いたい。「まるごと」の把握は半可通には出来ない。大技を決めておきながらしれっと何にも言っていないような顔をしている。実際何も言っていないじゃないか。いや、そこが凄いところなんだ。と空に向かってため息をつく。どうにもニクいのである。
↧
↧
俳句の自然 子規への遡行36 橋本直
俳句の自然 子規への遡行36
橋本 直
初出『若竹』2014年1月号(一部改変がある)
以前(第十八回)に触れたように、子規の「俳句分類」は、約十年の間に十二万を超える近世の句を収集・分類している。これはおそるべき数字で、単純計算で一ヶ月あたり平均一千句を分類し続けたことになる。この間、子規は病床の人になったことを考えれば、そのペースの異様さはただ事ではないのがわかるであろう。
なぜ子規が分類を始めたのかについては、前に既出の説を紹介した。また、そのほかの子規の評伝類でも「俳句分類」が大仕事であったことに触れてあっても、子規の業績との関連は案外に通り一遍の解釈で済まされているように思われる。それらが一応は筋が通った説明でも、なぜにこの異様な仕事が継続されえたのかについて、どうもなにかひっかかり、私には腑に落ちなかった。
簡単に言えば、季語を軸として何が何と組み合わされているのかをひたすら集めて分類するだけのこの作業は、なんでもないことであったかのように大変なことが継続されているのである。しかし、子規はそれなりに高い収集分析能力はあるかもしれないが決してスーパーマンではない。分類し終わったすべてを記憶してもいないであろう。十二万句も集めてしまえば、それが作句のためにあるというなら、逆にその情報をもてあましたのではないのか。しかし子規は健康状態がそれを許さなくなるまで分類をやめられなかった。そういう子規の思考行動を理解するために、自分の視界に入ってくる人の行為の中で、この情熱のありかたに似ているものは何だろう、とずっと考えていたが、ある時、以前に読んだ記事をはたと思い出した。解剖学者の養老孟司氏のことである。それは氏の専門領域の話ではなく、趣味の昆虫採集であった。氏はゾウムシ、特に普通種のクチボソゾウムシを収集されている。
〈ふつうの人は「なにか珍しいものが採れましたか」とすぐに尋ねる。しかし「珍しい」ということがわかるには、「普通」がわかっていなければならない。普通種がわからない人に、珍しいものを説明しても、じつはわかるはずがない。(養老孟司「養老孟司先生のタケシくん虫日記」日経ビジネスオンライン2007年10月17日)〉
子規もちょうど、昆虫学者が昆虫を収集し、調べ、ひたすら普通種を集めて同種か異種かを判別し、ごくまれに新種珍種を発見してゆくように、俳句を収集し続け分類しているように見える。中でも、養老氏のように昆虫採集を好む人が素人には同じようにしか見えない「普通」の虫を執拗に集め続ける情熱が、子規の分類作業のそれに重なって見えたのである。それはどういうことであろう。
この自然科学的な方法は、初期の段階であれば、ひたすら種類を集め、分類し、区分け(術語、用語としての名付け)してゆくことで、微細な差異が顕在化し、それが積み上げられて「学」が成立することになるだろう。そして集めれば集めるほど「学」としての厚みは増してゆく。つまり正確さを期すためには、律儀にすべて集めざるを得ない。また、このような「科学的」態度をとるとき、たとえば珍種の蝶が高値で取引されることがその態度の枠内においては無化されるように、芭蕉が俳聖であるとか言う「個」の歴史的価値はその枠内において無視されることになるであろう。そしてそのように同質化されることによってある意味で客観的な視点で句群に向き合う視点を獲得することもできる。
子規によって芭蕉が〈正しく〉批判し得るのは、明治の旧派宗匠への批判ということなどは、本当は小事に過ぎぬ副次的なものであって、近世以来の俳諧の既存の評価の価値体系をまるまる無化でき、かつ「学」としての子規の個のレベルを越えた体系的もくろみがそれを担保するからではないのか。そしてすべて集めきって系統分類できてしまえば、一つの記号の体系となり、近世の俳句(俳諧の発句)はすっかりカタログにおさめられて、いわば「俳句学」として大成者たる子規とその後継者のものとなるであろう。それは、新しい「詩」たる近代俳句の踏み台になるはずのものだ。
しかしながら、それはただ集める「学」というだけではすまないであろう。昆虫であれば、その構造から生きていた時の様子を色々想像できる。それで不明の部分は現場に出て生態を観察することになるだろう。子規の俳句分類であれば、句が同時代の文脈に置かれたときどう読まれていたか、いまならどう読めるかを考えることにもなるだろう。そして言葉によって書かれたものおいて現場に当たる、読者と時と場所によって変容する相(アスペクト)の局面を無視はできない。それは最短詩型の俳句であればなおさらのことである。成立した「学」が継続してゆくには、その「正しさ」そのものを永遠に追い求める宿命が待っている。
そう考えてくると、以前(第二十三回)で述べたように、子規の最も数多く詠んだ句が、雪月花(梅)時鳥をはじめとする古来より歌われてきた各季節の代表たる季語群であった理由も、よりはっきりしてくるように思われる。個人の嗜好で詠んでいった結果がそのようであることはあまりにできすぎている。おそらく子規は、先に述べてきたような意味での科学者的な態度で俳句の「正しさ」をおいもとめ、自身の詠むべき季語すら意識的に選んでいたのではないのだろうか。
↧
BLな俳句 第5回 関悦史
BLな俳句 第5回
関悦史
少年の腕真すぐなる鳥兜 加根兼光『句群po.1―半過去と直接法現在として、あること』
鳥兜はいうまでもなく毒草ですが、青紫の花がすっきりと鮮明。
「腕真すぐなる」と捉えられた少年は鳥兜のイメージと重なり合いますが、過剰な攻撃性は持ち合わせておらず、ほっそりとした植物的な静かなたたずまいの中に毒の力を秘めていることを窺わせます。
句の言葉自体も五七五に無理なく収まって端正ですが、少年の本性ともいうべきものが、その存在感を通して把握されています。ことさら賛美したり、心情的に寄っていくのとは別の、なめらかながら硬質で理知的なアプローチによって核心に触れていると言えるでしょう。
若竹や稚児美しき鞍馬寺 村上蛃魚『夜雨寒蛩』
この句の「若竹」も写実的に寺の背景を成していますが、「稚児」のイメージを健やかで清潔なものにすることに役立っています。
鞍馬は牛若丸(源義経)が修行した地であり、この稚児からは牛若丸の容姿への連想も働きます。
この景は、鞍馬寺が閲してきた歴史的歳月と、そこでの人々の営みが、稚児の姿を取って不意に目の前にあらわれたようでもあります。「稚児」はいわば、古い謂われを持つ寺院がそのまま若くみずみすしいものとして生き続けているさまを体現しているので、「美しき」が空疎な外見賛美に終わっていないのはそのためでしょう。無欲でやわらかい心性のみが受け止めることができた美しさです。
作者の蛃魚は、土屋文明の師であった歌人村上成之の俳号。最近、林桂により「ホトトギス」への投句が句集『夜雨寒蛩』にまとめられました。
少年の耳に飼われている蛍 対馬康子『純情』
はかなげで、それゆえに異類との交感もできるという、死の影を帯びた繊細な少年像です。
しかしなぜ耳に蛍なのか。
「恋に焦がれて鳴く蝉よりも鳴かぬ蛍が身を焦がす」と都都逸に歌われたとおり、蛍は鳴き声を発しません。光るだけです。つまりこの少年は、自分の耳に飼っている蛍を、聴覚的には感知できない。しかし、にもかかわらず、蛍は勝手に住みついているのではなく「飼われている」。ならば少なくとも飼っている少年の側は自覚的なのではないか。
少年は蛍の意思を、聴覚とは別の回路で聴きとることができるのかもしれません。普通、飼うとはいっても虫を相手に感情的な交流を求めることはありません。犬や猫ならばともかく、生物としての次元が違いすぎ、交流のしようがないからです。なのになぜこの少年と蛍には交流があるように見えてしまうのか。
それは少年ではなく蛍の側を主体にしているからです。「少年が耳に蛍を飼っている」では、句の意味合いは全然違ってしまい、蛍は単に飼われている虫というだけの存在となります。ところが蛍(それも普通ではない場所にいる)の方を中心化することによってそちらも人格のようなものがあるかに見えてしまい、それと奇妙な関係を結ぶ少年も、何かの精のような不思議な透明感を帯びることになるのです。
しかし、飼われている蛍は果たして自分の居場所を自覚しているのでしょうか。この辺が昆虫ならではの謎めいたところで、二者の間には普通の意味での交流も関係もじつはないのかもしれません。自覚せずして飼い、身のうちに住まわせる。そこから、自分が関係すべき相手と引きつけあい、ともにいるのに多次元的にすれ違っているような切なさも淡く漂ってきます。
秋光に遠き落馬の騎手二十歳 対馬康子『純情』
同じ二十歳でも与謝野晶子の《その子二十歳櫛にながるる黒髪のおごりの春のうつくしきかな》の量感あふれる堂々たる自足ぶりと比べると、落馬の騎手の「二十歳」は身体の躍動の果ての事態であるにもかかわらず、なんと脆くてか細いことか。
秋光をまとうことで男性の身軽な身体の哀しさが美化されますが、あくまでも遠くから見守るのみで、落馬の実際の痛みや恥辱には寄り添えない。見ている側の美化がそのまま酷薄や無力感に転じてかねない場面ですが、己の内奥へと刃が返る寸前に一句は素早く完結し、切り取られた景のみが残ります。
少年のうしろの蛇の青光り 鳴戸奈菜『露景色』
どう見ても少年に狙いをつけていますね、この蛇は。
眼が光ったといった程度ではなくて、全身が青光りを発している。ただものとは思えません。
少年の背後に光沢ゆたかな蛇がたまたまいただけともとれますが、そう見えなくしているのが「うしろの」の「の」でしょう。「に」ならばまだ狙い澄ましているとまでは言いきれませんが(「に」には一点に引きしぼる効果があるので、蛇がそこから動きそうになくなる)、「うしろの蛇」で、少年と不可分なかかわりを持った蛇になります。
あえて少年に危険を教えずにその先が見たいという人もいるかもしれません。
人去りて一つになりし芋の露 宇佐美魚目『薪水』
サトイモの葉に乗った水の玉が流れ、一つになる。
どうということもない出来事のはずですが、「人去りて」が怪しい。人目を忍ぶというよりも、人が感知することを許されない世界での、とても純一な無性別の官能に触れている気がします。
宇佐美魚目といえば、澄んで落ち着いた閑雅さの向こうに非人間性すれすれの官能性を閃かせる名手であり、この句も《すぐ氷る木賊の前のうすき水》《白昼を能見て過す蓬かな》などの名吟に通じる冷やかな艶があります。
神の蛇にはよお眠りと老のこゑ 宇佐美魚目『紅爐抄』
こちらも少々俗界離れした、神仙じみた二者のやり取り。
「老のこゑ」は作者その人の声なのかもしれませんが、普通の人間とは思えない。
「神の蛇」が「眠る」という事態も、ただの冬眠ではなく、何かもっと大きなものの位相がうつろっていく風情。
「老のこゑ」の主の「老い」も春の到来とともにみずみずしく若返りそうでもあり、あるいは「老い」といいながらも姿かたちは一向に衰えないファンタジックな不死の存在のようにも思えます。あまり同類の多くなさそうなそうしたものたちが示しあう慈愛の、孤心と、世界大の融和に裏打ちされた格別の味わいを汲むべき句でしょう。
家畜車にただひとり滲(メンスト)血(ラチオン)の少年 安井浩司『赤内楽』
異様で無惨な状況の少年です。人間扱いされていない。「家畜車」に乗せられ、着いた先で一体どういう目に遭わされることか。無事に済むとは思えません。
さらに異様なのは「滲血」でこれに「メンストラチオン」とルビが振ってある。これは通常、月経を指します。男性とも女性ともつかない、というよりどちらからもはじき出されて性的アイデンティティを持ち得ない「ただひとり」の少年と、そこに降りかかる災厄と暴力の予感。
「BL」の呼称が発生する前のマンガや小説には、拒食への親和など、自身の肉体への拒否感が潜んでいる表現がときに見られましたが、この句の孤独感にはそれに通じるところ、違うところが複雑にまざりあっています。
少年や涅槃前夜のみなおみな 安井浩司『阿父学』
「涅槃」を季語としてとれば、陰暦二月十五日、釈迦入滅の日の法会を指すことになります。季語でないととった場合は、いろんな意味が重なっているものの、おおむね、煩悩の火が消えて、苦がなくなった状態となる。どちらかというと季語的な(つまり毎年繰り返される)意味に限定せず、この少年たちにとっては一回限りのことととった方が、この句の内圧が高まる気はします。
「おみな」という語感のやさしさも掬すべきでしょう。
寂静の境地にいたる前夜、少年たちは「おみな」となる。性的には攪乱されているにも関わらず、彼らは不思議な透明感と安らぎを漂わせています。「前夜」の緊迫感とのコントラストにもよるのでしょう。
男性、女性両方の位格を経た少年たちの、その先に待つもの。そうした形でイメージされた涅槃はどこか異教的な匂いも漂いますが、なぜか若いまま「涅槃」に入ってしまう少年=おみなたちには、無垢なるものの印象が強く、それが同時になまめかしい。
そしてこの、涅槃への階梯を含んだ世界も、奇怪ながら柔らかい包容性に富んでいて魅力的です。
師と少年宇宙の火事を仰ぎつつ 安井浩司『宇宙開』
安井氏の句について書き始めたところへ、ちょうど最新句集『宇宙開』が届き、さっそく開いてみたらこの句があって、その壮大で奥深いヴィジョンに打たれました。似た感銘を与えてくれるものは、他の芸術ジャンルを探してもウィリアム・ブレイクの絵画作品など、ほんの一握りなのではないでしょうか。
少年は一応出てきますが、もうBL的かどうかとかは正直どうでもいい。あえてそこに気をつけて見た場合でも、この句の眼目は師と少年との関係にはならない。「師」が求道性を導入しているのですが、その庇護を受け、導かれながら「宇宙の火事を仰ぎ」得る存在という少年像の呈示の方が主になるでしょう。「銀河鉄道の夜」のように、現世の外へ漂い出しながら真を求める、純粋で高潔で、しかも感じやすい魂を宿したものとしての少年です。
単なる天体の爆発ならば自然科学の文脈におさまってしまいますが、「宇宙の火事」は明らかに別次元の出来事です。ジャンルファンタジー的な想像力に通じるところもないではありませんが、この「火事」の光に身をつらぬかれるような観念性は、ジャンルファンタジーの担いうるところでもないでしょう。
そしてそのヴィジョンが大いなるものであればあるほど、それに見入る少年の心身のはかなさ、やわらかさが際立ってくる。この句から少年美を掬いとるとしたら、このヴィジョンにつらぬかれる心身の、この世のほかの透明感をおいてほかにはありません。
安井浩司の句も近年、息詰まるような不吉な緊張をもたらすものは少なくなり、安らかにたゆたう開放感のあるものが増えてきましたが、この句も「仰ぐ」という垂直な精神性を持ち、畏怖すべき巨大な事象を描いていながらも、句のありようとしては、深々と息のできる、その中でいつまでも遊べるような時空を現出させています。
*
ペットボトル 関悦史
解氷は石田彰の声したり
春の雲女の子たちはうるさいねぇ
春光差すペットボトルの水 「察して」
友達と重なつてみる春の昼
新草(にひくさ)を付け友達と起きあがる
春セーター脱ぐ筋肉の動きけり
京浜線山手線春を併走し
少年の佐保姫のみが立つ列車
己を撮る偽娘(ウェイニャン)の腿春寒き
春風やミニスカートの偽娘(ウェイニャン)に
関悦史
『ふらんす堂通信』第140号より転載
少年の腕真すぐなる鳥兜 加根兼光『句群po.1―半過去と直接法現在として、あること』
鳥兜はいうまでもなく毒草ですが、青紫の花がすっきりと鮮明。
「腕真すぐなる」と捉えられた少年は鳥兜のイメージと重なり合いますが、過剰な攻撃性は持ち合わせておらず、ほっそりとした植物的な静かなたたずまいの中に毒の力を秘めていることを窺わせます。
句の言葉自体も五七五に無理なく収まって端正ですが、少年の本性ともいうべきものが、その存在感を通して把握されています。ことさら賛美したり、心情的に寄っていくのとは別の、なめらかながら硬質で理知的なアプローチによって核心に触れていると言えるでしょう。
若竹や稚児美しき鞍馬寺 村上蛃魚『夜雨寒蛩』
この句の「若竹」も写実的に寺の背景を成していますが、「稚児」のイメージを健やかで清潔なものにすることに役立っています。
鞍馬は牛若丸(源義経)が修行した地であり、この稚児からは牛若丸の容姿への連想も働きます。
この景は、鞍馬寺が閲してきた歴史的歳月と、そこでの人々の営みが、稚児の姿を取って不意に目の前にあらわれたようでもあります。「稚児」はいわば、古い謂われを持つ寺院がそのまま若くみずみすしいものとして生き続けているさまを体現しているので、「美しき」が空疎な外見賛美に終わっていないのはそのためでしょう。無欲でやわらかい心性のみが受け止めることができた美しさです。
作者の蛃魚は、土屋文明の師であった歌人村上成之の俳号。最近、林桂により「ホトトギス」への投句が句集『夜雨寒蛩』にまとめられました。
少年の耳に飼われている蛍 対馬康子『純情』
はかなげで、それゆえに異類との交感もできるという、死の影を帯びた繊細な少年像です。
しかしなぜ耳に蛍なのか。
「恋に焦がれて鳴く蝉よりも鳴かぬ蛍が身を焦がす」と都都逸に歌われたとおり、蛍は鳴き声を発しません。光るだけです。つまりこの少年は、自分の耳に飼っている蛍を、聴覚的には感知できない。しかし、にもかかわらず、蛍は勝手に住みついているのではなく「飼われている」。ならば少なくとも飼っている少年の側は自覚的なのではないか。
少年は蛍の意思を、聴覚とは別の回路で聴きとることができるのかもしれません。普通、飼うとはいっても虫を相手に感情的な交流を求めることはありません。犬や猫ならばともかく、生物としての次元が違いすぎ、交流のしようがないからです。なのになぜこの少年と蛍には交流があるように見えてしまうのか。
それは少年ではなく蛍の側を主体にしているからです。「少年が耳に蛍を飼っている」では、句の意味合いは全然違ってしまい、蛍は単に飼われている虫というだけの存在となります。ところが蛍(それも普通ではない場所にいる)の方を中心化することによってそちらも人格のようなものがあるかに見えてしまい、それと奇妙な関係を結ぶ少年も、何かの精のような不思議な透明感を帯びることになるのです。
しかし、飼われている蛍は果たして自分の居場所を自覚しているのでしょうか。この辺が昆虫ならではの謎めいたところで、二者の間には普通の意味での交流も関係もじつはないのかもしれません。自覚せずして飼い、身のうちに住まわせる。そこから、自分が関係すべき相手と引きつけあい、ともにいるのに多次元的にすれ違っているような切なさも淡く漂ってきます。
秋光に遠き落馬の騎手二十歳 対馬康子『純情』
同じ二十歳でも与謝野晶子の《その子二十歳櫛にながるる黒髪のおごりの春のうつくしきかな》の量感あふれる堂々たる自足ぶりと比べると、落馬の騎手の「二十歳」は身体の躍動の果ての事態であるにもかかわらず、なんと脆くてか細いことか。
秋光をまとうことで男性の身軽な身体の哀しさが美化されますが、あくまでも遠くから見守るのみで、落馬の実際の痛みや恥辱には寄り添えない。見ている側の美化がそのまま酷薄や無力感に転じてかねない場面ですが、己の内奥へと刃が返る寸前に一句は素早く完結し、切り取られた景のみが残ります。
少年のうしろの蛇の青光り 鳴戸奈菜『露景色』
どう見ても少年に狙いをつけていますね、この蛇は。
眼が光ったといった程度ではなくて、全身が青光りを発している。ただものとは思えません。
少年の背後に光沢ゆたかな蛇がたまたまいただけともとれますが、そう見えなくしているのが「うしろの」の「の」でしょう。「に」ならばまだ狙い澄ましているとまでは言いきれませんが(「に」には一点に引きしぼる効果があるので、蛇がそこから動きそうになくなる)、「うしろの蛇」で、少年と不可分なかかわりを持った蛇になります。
あえて少年に危険を教えずにその先が見たいという人もいるかもしれません。
人去りて一つになりし芋の露 宇佐美魚目『薪水』
サトイモの葉に乗った水の玉が流れ、一つになる。
どうということもない出来事のはずですが、「人去りて」が怪しい。人目を忍ぶというよりも、人が感知することを許されない世界での、とても純一な無性別の官能に触れている気がします。
宇佐美魚目といえば、澄んで落ち着いた閑雅さの向こうに非人間性すれすれの官能性を閃かせる名手であり、この句も《すぐ氷る木賊の前のうすき水》《白昼を能見て過す蓬かな》などの名吟に通じる冷やかな艶があります。
神の蛇にはよお眠りと老のこゑ 宇佐美魚目『紅爐抄』
こちらも少々俗界離れした、神仙じみた二者のやり取り。
「老のこゑ」は作者その人の声なのかもしれませんが、普通の人間とは思えない。
「神の蛇」が「眠る」という事態も、ただの冬眠ではなく、何かもっと大きなものの位相がうつろっていく風情。
「老のこゑ」の主の「老い」も春の到来とともにみずみずしく若返りそうでもあり、あるいは「老い」といいながらも姿かたちは一向に衰えないファンタジックな不死の存在のようにも思えます。あまり同類の多くなさそうなそうしたものたちが示しあう慈愛の、孤心と、世界大の融和に裏打ちされた格別の味わいを汲むべき句でしょう。
家畜車にただひとり滲(メンスト)血(ラチオン)の少年 安井浩司『赤内楽』
異様で無惨な状況の少年です。人間扱いされていない。「家畜車」に乗せられ、着いた先で一体どういう目に遭わされることか。無事に済むとは思えません。
さらに異様なのは「滲血」でこれに「メンストラチオン」とルビが振ってある。これは通常、月経を指します。男性とも女性ともつかない、というよりどちらからもはじき出されて性的アイデンティティを持ち得ない「ただひとり」の少年と、そこに降りかかる災厄と暴力の予感。
「BL」の呼称が発生する前のマンガや小説には、拒食への親和など、自身の肉体への拒否感が潜んでいる表現がときに見られましたが、この句の孤独感にはそれに通じるところ、違うところが複雑にまざりあっています。
少年や涅槃前夜のみなおみな 安井浩司『阿父学』
「涅槃」を季語としてとれば、陰暦二月十五日、釈迦入滅の日の法会を指すことになります。季語でないととった場合は、いろんな意味が重なっているものの、おおむね、煩悩の火が消えて、苦がなくなった状態となる。どちらかというと季語的な(つまり毎年繰り返される)意味に限定せず、この少年たちにとっては一回限りのことととった方が、この句の内圧が高まる気はします。
「おみな」という語感のやさしさも掬すべきでしょう。
寂静の境地にいたる前夜、少年たちは「おみな」となる。性的には攪乱されているにも関わらず、彼らは不思議な透明感と安らぎを漂わせています。「前夜」の緊迫感とのコントラストにもよるのでしょう。
男性、女性両方の位格を経た少年たちの、その先に待つもの。そうした形でイメージされた涅槃はどこか異教的な匂いも漂いますが、なぜか若いまま「涅槃」に入ってしまう少年=おみなたちには、無垢なるものの印象が強く、それが同時になまめかしい。
そしてこの、涅槃への階梯を含んだ世界も、奇怪ながら柔らかい包容性に富んでいて魅力的です。
師と少年宇宙の火事を仰ぎつつ 安井浩司『宇宙開』
安井氏の句について書き始めたところへ、ちょうど最新句集『宇宙開』が届き、さっそく開いてみたらこの句があって、その壮大で奥深いヴィジョンに打たれました。似た感銘を与えてくれるものは、他の芸術ジャンルを探してもウィリアム・ブレイクの絵画作品など、ほんの一握りなのではないでしょうか。
少年は一応出てきますが、もうBL的かどうかとかは正直どうでもいい。あえてそこに気をつけて見た場合でも、この句の眼目は師と少年との関係にはならない。「師」が求道性を導入しているのですが、その庇護を受け、導かれながら「宇宙の火事を仰ぎ」得る存在という少年像の呈示の方が主になるでしょう。「銀河鉄道の夜」のように、現世の外へ漂い出しながら真を求める、純粋で高潔で、しかも感じやすい魂を宿したものとしての少年です。
単なる天体の爆発ならば自然科学の文脈におさまってしまいますが、「宇宙の火事」は明らかに別次元の出来事です。ジャンルファンタジー的な想像力に通じるところもないではありませんが、この「火事」の光に身をつらぬかれるような観念性は、ジャンルファンタジーの担いうるところでもないでしょう。
そしてそのヴィジョンが大いなるものであればあるほど、それに見入る少年の心身のはかなさ、やわらかさが際立ってくる。この句から少年美を掬いとるとしたら、このヴィジョンにつらぬかれる心身の、この世のほかの透明感をおいてほかにはありません。
安井浩司の句も近年、息詰まるような不吉な緊張をもたらすものは少なくなり、安らかにたゆたう開放感のあるものが増えてきましたが、この句も「仰ぐ」という垂直な精神性を持ち、畏怖すべき巨大な事象を描いていながらも、句のありようとしては、深々と息のできる、その中でいつまでも遊べるような時空を現出させています。
*
ペットボトル 関悦史
解氷は石田彰の声したり
春の雲女の子たちはうるさいねぇ
春光差すペットボトルの水 「察して」
友達と重なつてみる春の昼
新草(にひくさ)を付け友達と起きあがる
春セーター脱ぐ筋肉の動きけり
京浜線山手線春を併走し
少年の佐保姫のみが立つ列車
己を撮る偽娘(ウェイニャン)の腿春寒き
春風やミニスカートの偽娘(ウェイニャン)に
石田彰=声優。『新世紀エヴァンゲリオン』の渚カヲル役等で知られる。
三句目は歌人荻原裕幸氏の、二〇一四年三月七日の自歌自解ツイートによる。
偽娘(ウェイニャン)=中国の女装男子で、日本では「ジャーニャン」とも訓まれる。
↧
【句集を読む】生きながら永眠する日、それから 鴇田智哉『凧と円柱』を読む 小津夜景
【句集を読む】
生きながら永眠する日、それから
鴇田智哉『凧と円柱』を読む
小津夜景
前回の書評で、わたしは鴇田智哉『こゑふたつ』の作句原理を「線を引くこと」「息をすること」「疵を負うこと」といった3つの切り口から分析してみました。またその際明らかになったのは、大筋で言って次のようなことでした。(1)作者の生み出すさまざまな形状の線は、そのつど時空の契機/継起となって〈バレットタイムとしての間〉を押しひろげること。(2)この〈バレットタイムとしての間〉は、息づくものの航跡とその痕跡を句中に残すこと。(3)さらにその航跡/痕跡というのが〈生きながら/死んでいる/ことを知る〉現在性そのものであること。
さて今回は『凧と円柱』の感想なのですが、これも「いきものは凧からのびてくる糸か」を筆頭に、前回確認された原理が色濃く引き継がれた句集とみて差し支えないでしょう。とはいえ同じ話をするのはつまらない。わたしは鴇田の作句の特色について、また別のあたらしい視点から語ろうと思っています。
0. ヴェールへ向かって
まず最初は、この作者によく見られる構図の作品から見てゆきましょう。
すりガラスから麦秋へ入りたる
ひだまりを手袋がすり抜けてゆく
ひあたりの枯れて車をあやつる手
こなごなに凍てながら日は水底へ
はじめの句は、白濁のガラスを通りぬける線(たぶん光を受けた視線)が、移ろいやすい初夏のさなかへと伸びてゆく光景です。いっぽんの、あるいはいくつもの線を描くことで句中に〈生ける間〉を創りだすこの書法は「畳から秋の草へとつづく家」をはじめ『こゑふたつ』にもっとも多く見られたこの作者の基本形でした。次の句は、日だまりをすりぬける手袋がふいに痕跡として作者に知覚されたようすですが、このあかるさ/通過/痕跡のとりあわせは前作「綿虫のとほりし跡のあかるかり」と重なりあう構図とみなせます。その次の句では「空の絵を描いてをれば末枯るる」と同じ作用、つまり手の動きによる〈生ける間〉の創出がなんらかの枯渇・痕跡化と共鳴しあうさまが詠まれていて、さいごの句は「ゆふぞらをつらぬく胼の体かな」の系譜、すなわち伸びゆく線からうまれる〈生ける間〉が、現在性を無限に引き裂くことによって成り立つがために、それ自体の亀裂を同時に引き起こす原理に倣っているようです。
ところで今見た作品は、これまでの手法を単になぞっているだけでなく、実は『こゑふたつ』では印象としてしか語りえなかったこの作者の別の個性が、はっきりと押し出されたものでもあります。もういちどよく見てみると、ここでの麦秋はすりガラスという〈ぼんやりした光の膜を潜って〉現れ、手袋はひだまりという〈たゆたう光の泉を通って〉動き、車をあやつる手はひあたりという〈照り映える光を伝って〉働き、日は水中の〈ゆがんだ光を貫いて〉伸びながら砕けている。つまり作者は〈伸びる線〉と関係する〈生ける間〉の様相を、ある一定の〈ディアファネースのイメージ〉と絡めて表出しているのです。
ディアファネースとはディア(~を通して、~を介して)+ファイノー(現す、現れる)から成るアリストテレスの造語で、視線と対象との間にあって「見ること」を可能にする透明な領域を意味します。もっとも岡田温司の研究によると、アリストテレスの意図する透明性は目に見えないそれではなく、かなり幅のある光のグラデーションが想定されており、実際には半透明性とみなすのが適切とのこと。岡田はその著著『半透明の美学』で、この語の歴史的な使用例をさまざまに列挙します。たとえば聖書では大気、雲、煙、水晶、天使といった語が見えるものと見えないものとを媒介する役割を果たすディアファネース=半透明性とされ、また人間の言葉のあいまいさに注目したダンテはそれを ineffabilitade(汲みつくしがたさ)だとか corpo diafano(半透明な物体)などと呼んで、動物的なもの(叫び)と天使的なもの(沈黙の言語)との間に位置するディアファネースとみなしました。さらに岡田は彼自身の考えとして、メルロ=ポンティが物の見え方を歪ませる水中という場を「肉」にたとえ、それを「見る側=自己」と「見られる側=世界」との間にある半透明の膜、襞、ヴェールであるとしたことを、ディアファネースの系譜につらなる思想だと述べています(少し註釈すると、肉がヴェールであるというのは「神のヴェールを纏うと、イエスが肉体を着る(受肉する)ことになった」話に由来する西洋に古くからある見立てで、聖書では「イエスは、垂れ幕、つまり御自身の肉を通って、新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです」〔ヘブライ人への手紙10章20節〕といった風に使われています)。
壜ならばすんなり秋が来てくれる
ひなたなら鹿の形があてはまる
1. ヴェールのゆらめき
鴇田智哉『凧と円柱』の最大の特色、それはこの半透明性をめぐる語がほとんどの句で確認できることです。さいきん出たばかりの本ゆえ引用にはいささかの節度が必要ですが、そうした制限の中で、作者のイメージの普遍的な型をさぐってみたいとおもいます。
まちなかにこまかい塵の降るむかし
まなざしの球体となり霧をゆく
ひとつめは、作者が「塵」という語を「街中に降るもの」の意味から「降りつもる月日」の隠喩へとずらしうるよう巧みに配したことで、句全体が「歳月のヴェールに覆われた街」を遠望するかのような佇まいとなった作品です。むかしという場所はふつう肉眼で見ることのできないものですけれど、そこを作者はあるようでないようなヴェール、すなわち〈こまかい塵を介して〉、経験の領域(街)と想像の領域(昔)とを手品のように結びつけます。そして勿論ここで注目すべき点は、この塵という微小な粒子の膜が〈現前しつつ不在する半透明性〉の概念をわかりやすくイメージ化した図像学的な働きを担っていることに他なりません。
この図像のヴァリエーションとしては埃・煙・粉・灰・雲・霞・雪などがすぐに思い浮かぶことでしょう。またそこから上のふたつめの句で「霧」という〈こまかい水煙を通って〉まなざしが移動する際も、作者がこの語に〈現前しつつ不在する半透明性〉のメカニズムを担わせていることがおのずと見えてきます。加えて掲句は、霧の影響をうけて球体となったまなざしの描写が、水晶に映りこむ催眠的世界のイメージを召喚してもいるようす。私はこれを読んだとき、ああそういえば眼にも水晶体がついていたなと思いつつ、あたかも眼球までがダンテの言う corpo diafanoと化した気分になりました。ものを見るとは〈間〉という〈意識の虚ろな泉〉を創り出すことであると同時に、その泉におけるものの見えにくさ(汲みつくしがたさ)と出会うことでもあるといったありさまが、この句ではなかなか手の込んだ形で語られているようです。
いちめんの桜のなかを杖が来る
うらうらと人のうねつて紙が散る
鳴りわたる時報に葛のはびこれり
2. ヴェールの肌ざわり
ところで、こうした半透明性は大気中をかがようだけではありません。すでに「街中にこまかい塵の降るむかし」における「塵の〈ヴェールをかぶった〉街/昔」等いくつかの構図をみていますが、この本のそれはものを遮るだけでなく、ものを覆ったり、ものに巻きついたり、ものと絡みあったりしながら複雑な世界を造形する皮膜ないし肉襞的な表象としても機能するようです。つまりディアファネースは、主体からも客体からも独立した領域であると同時に、しなやかな界面としてそれらと相互に深く綾なしてもいる。「肉とはまさに、わたしの身体から剝ぎ取られ、世界からも剝ぎ取られて、お互いに巻きつき絡み合いながら複雑に襞を刻んでいる、半透明の皮膜のようなイメージなのではないだろうか。『ヴェールのない視覚などない』とは、ほかでもなくメルロ=ポンティ自身のせりふである」(『半透明の美学』)。
たてものに布のかぶさる蝶のひる
ハンカチが顔を包んでゐる正午
古典彫刻に「濡れ衣」の技法というのがあります。これは風にそよぎつつも身体にぺたりとくっついた「濡れ衣」を人体像に彫り込むことで、視線と対象との間に、対象を〈隠しているけれど暴いてもいる〉ヴェールすなわち〈現前しつつ不在の〉ディアファネースを出現させるというたいへん面白い手わざです。当時の文脈において、人物像がなんらかのイデアの具現だったことを考慮すると、このような表現法は「真理というのが常に〈透かし見る〉ことしかできない姿で主体の眼前にある」ことの寓意として発展したのかもしれません——といった想像はさておくとして、上の句などはこの「濡れ衣」的アプローチと見て差し支えない作品でしょう。かぶさる布ないし包むハンカチいった発想は、とりもなおさず主体と客体とのあいだにある半透明の界域の概念をそのままメタフォリカルに意匠化したものだ、というわけです。
包帯の巻きついてゐる冬日かな
上着きてゐても木の葉のあふれ出す
風船になつてゐる間も目をつむり
ここでは包帯、上着、風船といったディアファネースが皮膚的な様相を呈しています。私はこれらの句を、この作者の皮膜フェティシズムがあからさまにあらわれたものとして読みました。
はじめの句は前作「西風は人の襟巻かも知れぬ」と同型の作品。「西風」ではディアファネースが自己の側に巻きついていて「冬日」では世界の側に巻きついているという細かい差はありますが、どちらも西風や冬日の表面に、自己や世界とじかに触れあう襟巻ないし包帯らしき半透明性を感じた、という作者の体験です。
次の句は、そのまま文字どおりに解釈するとなんだか思弁的で素敵なのですけれど、おそらくそうではなく、もっと単純に、上着をきている作者が目の前の木の葉を、あたかも自分の体から出ているような気分で眺めている光景だと思われます。メルロ=ポンティのいう「見るものと見えるものとの間の可逆性」に基づいた構図は、残像の留まる場であるまなうらに目そのものが映ってしまった「春の蚊が浮きまなうらに目のありぬ」や「水母を見ている目」を洗う気分で「目に見えている水母」を洗っていた「目を洗ふやうに水母を洗ふなり」など『こゑふたつ』でも定石でしたし、たぶん間違いありません。ちなみにこの句に関して一点、作者に代わって本当のことを言うと、上着を着ていても、ではなく、上着を着ているから、木の葉が身体から湧出するのです。なぜなら鴇田の場合、自己と世界との入れ換えは、両者のあいだに介在するディアファネースを見る(触れる)ことで起こりうるのですから。
さいごの句は、作者が目を閉じて風船という半透明の膜になり、ふわふわした意識の感触を味わっている光景です。これも作者が風船を見ていたようすが原型にあるとおもわれますが、実はこの句にはそこで話を終わりにできない要素が見られます。わたしの直観では、作者の体が風船と化したこと、つまり鴇田その人が全身ラバースーツとおぼしき形に生まれ変わって、おのれをすみずみまで触覚化するに至った理由を考えてみなくてはいけない。要するに鴇田智哉が「受肉」ならぬ「受ゴム」したことの意味がきわめて重要なのです。
この意味について、わたしはこう考えてみました。曰く、自分以外のものを感覚することのできない全身ラバースーツとなって目をつむるとは「本人が、唯一の世界である本人自身との間にディアファネースを創造し、かつそれを愛でる」ことに他ならない、と。
これは半透明マニアにはたまらない状態のはず。だってふつうは半透明の領域だけを見たいと思っても、その向うにある光景がいかんせん目に入ってしまうのですから。けれども前回の書評を引くなら「鴇田は世界の内部ではなく(また外部でもそれらの境界でもなく)その契機、すなわち〈私と世界とが未分化のまま生きられる現前〉の位相へ自らを関係」させたい作家です。また同時に、この未分化幻想が私と世界とを互いに触れ合わせるディアファネースなくしては(つまり私と世界とをいったん分離するものなくしては)成立し得ない思考上のパラドックスであることも当然心得ているでしょう。それが「受ゴムによる、自己の、自己への関係」という発想に立つだけで、究極の〈私と世界とが未分化のまま生きられる現前〉との戯れがすんなり可能になる。
風船という〈半透明の皮膜〉になった作者。それは膨らめば膨らむほど、意識の浮揚感を増してゆくことでしょう。またそのときゴムの膜は薄くなってゆくので、身体は八つ裂き感を強めることになります。つまり風船とはそれ自体がディアファネースであることに加え、私と世界とが未分化の場所で引き伸ばされると同時に引き裂かれてゆくという〈生きながら/死んでいる/ことを知る〉時空の原理そのままを目に見える境地に実現したすごいアイテムだったのです——正直わたしにはなんのこっちゃですが、これまで鴇田の示してきた諸々の偏愛をしかるべき角度から再構成するに、おそらく彼にとってこのゴム製遊具になるというのは、大変申し分のない快楽なのではないでしょうか(他にも、全身ラバースーツは時間の感覚が奪われるという意味で、まさしく生きながら死んでいる感覚を体験できる(らしい)のですが、話が悩ましい問題に発展しかねないので差し控えます)。
3. ヴェールの起こり、そして名ごり
ここまでディアファネースのさまざまな在り方として、ものを遮る、ものを覆う、ものに巻きつく、ものと絡みあうなどの様態をみてきました。さらにこの半透明性そのものの虚薄性(平たく言えば、気配としての薄さ)についても、いま少し確認してみたいと思います。
はだいろのとけこんでゐる竹の春
冷えて木は一本立つてをりにけり
円柱は春の夕べにあらはれぬ
これらは竹、木、円柱といった線の表象物が、あってなきかの幽霊さながら痕跡化された光景です(余談ですが、鴇田は花には具体名を与えるのに対し、木はいつも無名です。これは彼にとっての木の価値がなによりもまずその線的表象にあることを強調するため、余分な情報を拭い去っているのだと思われます)。そして、やはりこの場合も、作者の視線とこれらの線形体とを媒介するディアファネースはあいまいな、ぼんやりとした、模糊的特色をもっています。竹の句は色がとろけ、木の句は冷気という白濁性を帯び、そして円柱の句は「あらはれぬ」とある以上、暮靄に満ちているとみなして構わないでしょう。ここでは見るもの(視線)も見られるもの(対象)もディアファネースの肉襞に織り込まれてしまっているせいで、円柱は偶発的にあらわれる(そしておそらく消える)ように感じられるのです。
ここで留意したいこと、それは何かが現れてくると同時に消えてゆくような掲句の景色が〈はじまりのようでもおしまいのようでもある間〉の潜勢力を再現している事実です。この潜勢力は、ディアファネースが五感に関係するヴェールであるだけでなく時空のヴェールでもあることの、今までとはまた別の角度からの証明となりえます。ちなみに、この時空のヴェールは「起こり」あるいは「名ごり」をめぐる察知として描かれることが多いようです。
七月の舌にかすかな味がする
あふむけに泳げばうすれはじめたる
春昼のだれもの曲がる角のあり
前触れが葱の花よりただよへり
かすかな味、あるいはうすれはじめるといった痕跡ないし兆候。みんな曲がるけれどその先は見えないといった、確実性と不確実性とのないまぜになった角の気配。察知をめぐるこうした感覚は時と場合に応じて描写される経験的な叙述ではなく、つねにこの作者についてまわる先験的な条件です。さいごの句では、密集花の雲ないし埃のような葱坊主が「前触れ」を漂わせる作用をもつことがはっきりと書かれ、ディアファネースの虚薄性について鴇田自身が素直に告白した一例となっています。
裏側を人々のゆく枇杷の花
木の揺れを覚まさうと日の裏手へと
この「裏」というのも、視線と対象との境界をゆれうごくいわばディアファネースのカーテンです。このカーテンは一瞬に凝縮された起こり/名ごり(つまるところ契機/痕跡)の光速反転を、その微細な揺れによって読者に察知させたり、また「花」と「人の流れ」との感応をうみだす影のうつろいや「日」と「木の揺れ」との共鳴をつかさどる光のかがよいを具現したりと、さまざまな「時空をめぐる、虚薄な気配」を句にもたらし、作品の風景を根幹から支えています。
・
かくのごとく『凧と円柱』は、さながらディアファネースの標本箱と言うべき句集です。見ておくべき構図や語彙はまだ沢山ありますが、すでに結構な数の句を引用してしまいましたので、最後にわたしがこの本でいちばん好きだった半透明性について感想を述べて、ひとまずこの書評はおわりにしたいと思います。
わたしが一番好きだった半透明性。それは「子供」でした。その理由は作者がこの小さな存在を、具象と抽象とのあいだにあるえもいわれぬ気配として扱っていたためです。
いちじくを食べた子供の匂ひとか
からすうりの花に子供のゐてしまふ
おぼろなる襞が子供のかほへ入る
『こゑふたつ』の「十薬にうつろな子供たちが来る」では、子供という語は「実在と非在とを兼ねそなえた亡霊のごとき痕跡」として機能していました。『凧と円柱』ではこの視座がいっそう鮮明になったらしく、ここに掲げた子供のすがたは可視性(生者)と不可視性(死者)との中間項である半透明的存在としてありありと読者に差し出されています。鴇田の子供たちは、もはや「うつろな」という形容詞を必要としません。そうした属性は、彼らにおいて完全に内在化してしまったのです。
はじめの句は、いちじくを体内に吸収した子供がたいへん独特な痕跡化を果たした光景ですが、匂いのヴェールを纏う子供といったくすぶる余熱のような亡霊性は、意味を宙づりにした措辞「とか」によってさらに余韻を深めています。また次の句では、なんとからすうりの花の煙じみた半透明性に子供が発見されている。しかしこれも、作者がふだんからあの小さい人たちのことを、この世のものでいてそうでないような一種の余韻として眺めているからだ、とわたしには思われてなりません。
そしてさいごの句。これはそれ自体がディアファネースの織物だとしか形容しようのない作品です。というのも、ここではおぼろな襞(まちがいなくほの暗い光)といった半透明のヴェールが、生者と死者との中間的表象である子供の、あるようでないような「かほ」に差し込むというただそれだけの——とはいえその差し込みによって存在の意味、すなわち生きながら死んでいることの意味が柔らかく切り開かれてゆく神秘的な——光景が描き出されているのですから。
いくつものディアファネースを折り重ねて造り上げた、くぐもる宝石。あるいはかがやく埃。この句はそういったものにどこか似てはいないでしょうか。
ここには〈半透明性〉という切り口のみが辿りつくことのできる淡い煙のような、かすかな香りのような、ほのぐらいステンドグラスのような、いわば〈不安定なイマージュ〉に秘められた安らぎへの配慮が溢れています。そして確かに、思い返してみれば子供というものが大人に与える不思議な安息も、その種の〈定まることのない存在の気配〉こそが人にもたらすカタルシスなのでした。
 |
Tomoya Tokita, Untitled, 1995 |
 |
Marcel Duchamp, Draft Pistons, 1914 |
↧